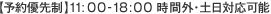相続税の豆知識
生命保険を使った相続税対策
生命保険会社のセールストークとして、相続税対策になる点が使われることがあります。これは死亡保険金には相続税の非課税枠があるからで、うまく使えば有効な相続税対策・納税資金対策になります。ただ契約の仕方によっては相続税対策にならないので、十分に気をつける必要があります。
死亡保険金に非課税枠がある
生命保険をかけていた被相続人が亡くなった場合、一般的には相続人が死亡保険金を受け取ることになりますが、死亡保険金は現金預金や不動産などの相続財産と異なり、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。非課税額が法定相続人の数に左右される点には注意してください。
法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。保険金が2,000万円の場合は、差し引き500万円が相続税の課税対象になります。
|定期保険・終身保険の他、傷害保険・少額短期死亡保険も可能
死亡保険金がおりる生命保険の定番としては、(60歳まで等)一定期間内だけ保障する定期保険、一生涯保障する終身保険があります。これらの保険金に関しては非課税枠があるのは当然ですが、他にも対象となる保険金があります。
生命保険でなく損害保険の分野になりますが、不慮の事故により保険金がおりる傷害保険は、死亡時も補償対象になることがあります。傷害保険の保険金は原則全額が非課税ですが、死亡時におりる保険金に関しては生命保険の死亡保険金と同じ扱いです。
また「葬儀費用保険」などの名前で、100万円単位(200~300万円が多い)の保険金額で死亡保障をつけた保険もあります。多くは生命保険会社でも損害保険会社でも無い少額短期保険業者が扱う保険になりますが、こちらの死亡保険においても同様の扱いがされます。
|契約の仕方には注意
相続税対策として活用するためには、生命保険・損害保険・少額短期保険いずれにしても契約の仕方には気をつける必要があります。
保険契約を行うにあたっては、契約者の他、保険料負担者・被保険者・保険金受取人を決めておく必要があります。被保険者に死亡などの保険事故があった際に、保険金はおります。
通常は契約者が保険料負担者になりますが、契約者以外の負担が認められる保険もあります。死亡保険においては、保険金受取人は被保険者と異なる人(通常は相続人)を指定しなければいけません。
保険料負担者・被保険者・保険金受取人の決め方によって、保険金に対する税金の税目も変わります。
|契約により相続税・所得税・贈与税のいずれがかかるか変わる
被保険者が保険料負担者となって保険料を支払い、相続人を保険金受取人にするのが一般的な死亡保険の契約形態ですが、これなら保険金には相続税がかかることになり、500万円の非課税枠も使えます。
例えば被保険者である夫が1,900万円の保険料を支払い、妻が2,000万円の死亡保険金を受け取るのであれば、この死亡保険金は夫から妻へお金が渡った(相続した)とみなされ、相続税の課税対象です。子が3人以上いるなど、法定相続人の数が4人以上であれば、全額が相続税の非課税対象となります。
ただ、別の契約形態も考えられます。夫が被保険者で妻が保険金受取人ですが、上記事例と異なり妻が保険料を支払うケースです。この場合は、妻が支払った保険料を原資にして、自分で保険金を得た形になります。保険金は妻の「所得」とみなされ、所得税および住民税の課税対象となります。
所得税・住民税の場合は所得分類により課税の仕方が変わりますが、死亡保険金は一時所得に該当し、下記のように計算します。
(保険金額 ― 保険料総額 ― 50万円)÷ 2
保険金額と保険料総額の差額が50万円以下であれば、課税されません。保険金額=2,000万円、保険料総額=1,900万円であれば、一時所得は25万円です。
住民税率は原則10%のため25,000円、所得税率は課税総所得金額に応じて増加します。高所得者と言える所得税率40%でようやく10万円になる程度で、保険料総額及び50万円の控除と2分の1特例により、保険金2,000万円の割に負担は軽いです。
さらに夫が被保険者で妻が保険料負担者ですが、保険金受取人が子のケースを考えてみます。この場合は夫の死亡により、妻から子に保険金が「贈与」されたとみなされ、保険金は贈与税の課税対象となります。
贈与税はもらった側が、他の贈与財産とあわせて110万円を超えた場合に納税します。子が保険金2,000万円以外の贈与財産以外ない場合、110万円を控除した1,890万円が課税価格となります。
この課税価格では、贈与税率45%(父母や祖父母から贈与を受けた場合の税率)になり600万円近い贈与税の納税となります。
相続税であれば、45%の税率は1人当たりの課税価格が2億円を超えた場合になりますので、贈与税を支払う形が一番損する可能性が高いです。
表:契約形態と税目のまとめ
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税目 |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | B | 所得税 |
| A | B | C | 贈与税 |
相続税対策としての活用法
|納税資金
相続税は財産に応じた課税ですが、基礎控除や債務控除などの控除もある上で最高税率55%ですので、むやみに高い税額になるわけではありません。ただ相続財産においては不動産の比重が高いことが多いため、豪邸を相続した場合など相続税が高くとも払えるだけの資金があるとは限らないのが実情です。
多くの現金預金を残しておけば、その中からも払える余地は出てくるでしょうが、不動産のように換金性の低い財産も少なくないことを考えると、非課税枠のある生命保険の活用は、納税資金を多く残しておく上で有効です。
|遺産分割対策
死亡保険金は、他の相続財産とは性格が異なっています。厳密には遺産分割可能な相続財産という扱いにはならず、受取人固有の財産として扱われます。
遺産分割の仕方によっては法定相続分どおりに相続しなくても構いませんが、最低限保障される相続割合である「遺留分」を侵害した形で相続が進むと、うまく決着しなくなる恐れがあります。
死亡保険金が遺産分割可能な相続財産で無いと言うことは、特定の相続人に保険をかけても遺留分を侵害する要因にならないということです。妻と長男・次男が相続人で、次男が介護に消極的だった場合、夫は妻と長男の相続分を増やしたいと考えるでしょう。増やす分を死亡保険で確保するという方法があります。
また前述のように、不動産を相続した相続人が多額の納税を迫られる可能性もあり、不動産を相続する人が保険金受取人になって納税資金に使ってもらうことも考えられます。
計画的な活用が必要
老後になってから契約できる死亡保険として、一時払い終身保険というものもあります。1回で多額の保険料を払いきった上で、相続の際に死亡保険金がおりるものです。
もらえる保険金額<払う保険料額となる「元本割れ」をしない限りは有益な商品なのですが、保険会社側が扱いたがらない商品になっています。終身保険は払った保険料が必ず戻ってくる貯蓄性の保険なので、保険会社側は運用により支払保険金を確保する必要があります。
ただ支払保険金額が契約時に決まっている保険契約の場合、保険会社も預かっている保険料を株式のような元本保証のないものに多く投資するわけにはいきません。主に国債に投資していますが、金利が低すぎるため運用益が確保しにくいのが実情です。
死亡保険自体は、死亡率低下により平成30年度に保険料が下がることも見込まれています。計画的に相続税対策をしていくのが望ましいですね。
〜知って得する!相続税の仕組み〜【養子にすると節税になる?】
「相続税は基礎控除があるし、財産がたくさんある人が対象だから自分は関係ないし、大丈夫!」と思っている方も、相続税について考えたことがない方も、相続税は身近なものになってきていることをご存知でしょうか?平成27年に税法が改正され、基礎控除額が大幅に変更されました。こうした改正に伴い、多くの方が相続税の課税対象となったのです。そこで、誰がどのように相続税に関係してくるのか仕組みを紹介してゆきます。
・被相続人(亡くなられた方)の血縁関係者は常に相続人
相続税が発生するとなった場合、まずは被相続人との血縁関係者が納税義務者となります。これは相続においても同じです。しかし、相続の場合相続人が増えるということはそれだけ「法定相続分」または「取り分」が人数分で分配されてしまいます。つまり、所有権が細分化されるため決議が必要になります。その上で相続税も計算してゆくことになります。
・相続税と法定相続人の関係
相続の場合において、相続人が多ければ多いほど遺産分割の協議が難しくなることが多いのですが、相続税というジャンルにおいては人数が多いことは「節税」へと影響してきます。なんで節税と関係があるの?と不思議に思いませんか?簡単に説明すると相続税の基礎控除は「基本控除枠」に合わせて「法定相続人の数x600万円」というルールが設けられているからです。つまり、相続人が多ければ多いほど控除額が増えるということになります。夫婦2人に子供が2人の場合において夫婦の一方がなくなってしまった場合、相続人は3人となり理論上の相続税基礎控除額は3000万円と法定相続人3人x600万円=1800万円を足した4800万円となります。別例として子供が4人だとします。先ほどの例に比べて法定相続人が2人多いことになりますね?当然単純計算で600万円x法定相続人2人=1200万円が控除額として換算されますので、6000万円が基礎控除額となります。法定相続人1あたりの持つ相続税の基礎控除額も、人数が増えると多額になるということを覚えておきましょう。
・いつも子供ばかりが相続人ではありません。
「相続人が増えれば相続税の基礎控除枠も増えるのはわかったけれど、実際には子供は多いわけでもないし、どうすればそんな適用が実現するの?」と思ってしまいます。確かに、子供が5人6人いれば相続税の基礎控除には余裕ができますが、そんな家庭ばかりではありません。そこで活用できる制度が「養子」という存在です。例えば婚姻関係時に生まれた子供で、離婚をしてしまい再婚をした場合には、どちらかに血縁関係のない子供が在籍します。この場合、実際の血縁関係はないものの「養子」として縁組をすることで「実の子供」としてみなされます。つまりは、相続時においても「法定相続人」「法定相続分」が提供される、正真正銘の子供として扱われます。
※養子の実の両親の相続発生時には、その相続の対象の法定相続人としても扱われます。
・相続人が多く登場するケース
相続人が多い場合というのは様々なケースがあるので、イメージをつかんでいただくために例をあげてみます。
子供がいない夫婦のうち、夫が被相続人(亡くなった方)とします。
夫婦の間に子供はいません。被相続人の両親はすでに亡くなっており、兄弟姉妹は5人います。この場合の法定相続人は妻と被相続人の兄弟姉妹5人の合計6人となります。しかし、兄弟姉妹の誰かが先に亡くなっており、その兄弟姉妹に2子供がいたとします。この場合、兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。本来相続するはずの財産権を相続人の血縁関係者である甥姪が代襲相続をすることとなるため、相続人がさらに2人増えます。つまり合計の法定相続人は8人となり、相続税の基礎控除額が3000万円に600万円x法定相続人8人=4800万円を足すと7800万円になります。基礎控除枠3000万円よりも、法定相続人が持つ控除額の方が多いという結果になります。
このように「子供がいない夫婦」や自分よりも子供の方が先に亡くなっており、その夫婦間に子供がいる「代襲相続人がいる」場合には法定相続人が増えてくることになります。しかし、同時に「相続」そのものの手続きも伴うため、十分に対策を考える必要があります。
知って得する?相続税2割加算制度
相続人が増えれば節税につながると言う「知って得する情報」でしたが、実はもう一つ知って得することがあります。それが「2割加算制度」です。2割加算という言葉、タクシーでも深夜料金に2割増しという制度あります。決して得するわけじゃないのでは?と感じてしまうかもしれませんが、知らずにタクシーに乗ってしまうと余計に損をするものです。損を知ることで損をしない方法を考える一歩にもなります。
相続税2割加算制度とは
簡単にいうと、本来相続財産を取得する相続人である「配偶者」「子供」「親」以外の方以外の方が財産を相続する場合は、2割多く支払わなければならないという制度です。夫婦間に子供がいれば当然配偶者と子供が相続人、子供がいない場合には、配偶者と被相続人の両親が相続人となります。しかし、これ以外のケースとして子供がいない夫婦の被相続人側の両親が先に亡くなってしまっていた場合は「兄弟姉妹」が登場したり、内縁関係にある妻や知人など、主に法定相続人としての関係を持たない方などが登場した場合には、相続税の2割加算が適用されることになります。
なぜ2割加算制度があるの?
相続には様々なパターンがあり、家庭事情などによっては相続人を指定せざるを得ない場合など、やむを得ないケースもあります。例えば、被相続人の配偶者や子供を通り越して直接孫に相続をさせた場合には、本来配偶者と子供が相続して、その後子供の相続を通じて孫が取得をするという2段階の相続税が加算されるという流れになります。しかし、親の世代で孫に相続をさせると相続税が1回分免除されることになります。それならみんな違う人に相続させれば、相続税が一回で済むんだからいいじゃない!となってしまわないよう、2割加算制度が設けられております。
孫の場合と代襲相続人の場合では2割加算の適用は異なる?
相続税を少しでも節税するために、1回分の相続税を免除して割り増し加算してでも孫に相続させよう!といっても、代襲相続の場合は2割加算は適用されません。被相続人の配偶者との間の子供が先に亡くなっていた場合は、その孫は「代襲相続人」として扱われるため、相続の順番を飛ばしたことにはなりません。したがって相続税が1回免除されるという話ではなく、本来の相続人という扱いになり相続手続き上何も不都合がないということになります。しかし、その孫が被相続人の孫でもあり、養子の子供という存在でもあった場合には、例外として2割加算が適用されることとなります。
その他2割加算される主な人
相続税が2割加算される人は、主に次のような人です。
- 兄弟姉妹の相続人
- 祖父祖母の相続人
- 遺言等で血のつながりがなく財産をもらう人
- 遺言等で財産をもらう孫
このような人が相続税を支払うことになる場合には、相続税は2割加算となります。
お墓、仏壇を購入すると節税になる?!
・人の死と相続のあり方
人はこの世に生まれた時点で人権を備え死亡を持って相続が発生します。
生前に持っていた財産については「所有権」によって保護されているため、勝手に処分をすることはできません。
時に名義が保存されている財産に関しては公式な手続きを行わなければ所有権が移転したと認められません。
万が一勝手に処分をしてしまった場合には、のちに相続人同士でのトラブルになったり、場合によっては罪に問われてしまう可能性があります。
これは、人間がなくなった後もその財産いついては保護されるべきという概念のもと、法律で保護されているのです。
・仏具は非課税?祭祀財産とは
相続の財産というのは金銭的価値を持つもの、実質的な価値はないもののその価値を保証されているもの、あるいはマイナスの財産(借金や負債など)など様々なものが存在します。
この「生前に所有していた財産」という線引きは専門家の判断が必要になる場合もありますが、まずは名義を保存されているものなど、発見しやすいものから探してゆくと良いでしょう。
相続財産というのは通常「相続税の課税」の対象となります。財産の中でも他に類を持たないのが「祭祀財産」です。
人間の「死」に伴う必要費用などがこれに該当しますが、これらは「非課税対象」になります。例えば、「仏壇」「お葬式」「お墓」などがこれに該当します。これらの課税対象外の財産を「祭祀財産」と言います。
・相続税がかからない財産の基準について
1)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
また仏具が黄金製(K18や750など純度を示す刻印のあるもの)であり、資産価値が非常に高いものについては、祭祀財産としてみなされない場合があります。
ここで注意していただきたいのが、仏具=非課税だから大丈夫!という認識ではならないのです。
祭祀財産と認められたものに関しては課税対象外という判断がもらえるのであって、勝手な認識で課税か非課税かを決められるわけではないので、注意が必要です。
・お墓の相続って?
民法第897条に「祭祀に関する権利の承継」というのがあります。
お墓の設置されている通称「墓地」は、通常の不動産とは少し違い「墓地」という選択肢のほか使えないように制限がされております。
そのため、墓地の扱いは所有者と地主という関係ではありますが、財産という扱いにおいては登場しない存在となります。第1項には「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」と記されており、法律で承継について記されていることから、あくまでも習慣に従うという前提があります。
仮にもお墓が「相続財産」だった場合、亡くなられた方の借金が多すぎたなどの「相続を放棄せざるを得ない状況」であった場合、相続を放棄するということになれば、お墓も仏壇も含めて「相続放棄」となり、初めから相続関係になかったものとしてみなされてしまいます。
そうなると、承継されることなく、先祖が途絶えてしまうということになります。
これはいかがなものでしょうか?ということで、祭祀財産については民法で承継について定められており、法定相続人や相続財産などの部類とは違い、承継に関する権利などを制限することはせず「習慣」に従うということを法令で定めることで、先祖が守られているのです。
・祭祀財産は相続税の節税と関係があるの?
結論から言いますと、関係あります。相続税の節税対策として注目を浴びており、「知っている場合に限り活用できる」節税方法になります。
あらかじめ節税を考える方であればたどり着く内容ではあります。そもそも相続税自体の認識が薄いため、興味がある方は自分で調べるなどのプロセスの中に登場するのが「節税対策」というキーワードです。
相続税のカラクリを簡単に説明すると、亡くなられた方の所有していた財産については、その財産を相続するものに対して「相続税の課税」を行うことになりますが、非課税のもに関しては課税を行うことはありません。
そのため、亡くなった段階での「課税対象相続財産」次第ということになります。亡くなってからでは「課税財産」となってしまうものでも、生前に非課税の祭祀財産として持っておくことで、その費用は相続財産から外れます。
言葉だけだと伝わりにくいかもしれないので、金額を仮定して例をあげてみます。
(ケース1)
亡くなったAさんは現金を4500万円持っておりました。相続人はBさんCさんの2人です。相続税の基礎控除は3000万円+(600万円x相続人2人)=4200万円となります。財産の4500万円から基礎控除を差し引くと、課税対象額は300万円となります。これは、所有していた財産が「現金」という「課税対象の相続財産」であるからです。
(ケース2)
亡くなったAさんは現金を4000万円持っておりました。相続人はBさんCさんの2人です。相続税の基礎控除は3000万円+(600万円x相続人2人)=4200万円となります。財産総額が相続税の基礎控除額を超えていないため、相続税は発生しません。
さて、2つのケースを考えた時「財産が少なければ相続税の課税の対象にならない」ということがお分かりいただけましたでしょうか。
しかし、お墓が相続税の節税と関係があるというのが今回の趣旨です。では、どうすればケース1の財産額で課税対象から外れることができるのかどうか、説明します。
ケース1の場合に課税対象額は300万円でした。これは現金という課税対象の財産であったがために課税されてしまいました。しかし、相続税課税対象外の「祭祀財産」があることを覚えていますか?Aさんは生前に、自分のお墓や仏具を300万円で購入しました。
すると財産は4200万円となりました。つまり相続税の基礎控除の範囲内で収まるため、課税の対象にはなりません。
これがお墓ではなく、金銭価値の高い「純金」などに換金していた場合、この純金が財産となり、相当金額分が価値として算出され課税対象となってしまいます。
祭祀財産だからこそ許される非課税枠の300万円ということをご理解いただければ、イメージはつかみやすいかもしれません。
・財産が減れば非課税になるのは当たり前じゃないの?むしろ損しているのでは?
本当にそうでしょうか?4500万円という財産のうち300万円を損失と考えるかどうかについて、節税の効果を知れば考え方が変わります。
仮に4500万円という財産を相続し、300万円を課税金額として申告を行い相続税を支払ったとします。
すると、本来の財産は4500万円だったのに、相続税分は国に納税しているため純財産額を下回っています。
その後に、自分たちで300万円のお墓を買ったとすれば、税金を納めた後の財産額から300万円という出費になり、税金分は実質マイナスとなってしまうのです。
生前に300万円でお墓を買っておけば、相続税を課せられることなく、4200万円の純資産プラス300万円分の祭祀財産を取得します。
しかし、相続発生後に相続税が発生し、300万円のお墓を買ったとすると300万円から相続税は引かれてしまうため、支払った税額を4200万円から補わなければ300万円の祭祀財産を購入することができません。
同じ金額のものを買うにしても、納税というマイナスが発生するかしないかという大きな分かれ道になります。
本当のマイナスは「対策すれば払う必要のなかった税金額」であり、生前の購入金額分ではありません。いずれは必要になる祭祀財産などの非課税財産を生前に買うことで、財産額を落とし相続税の対策として活用することもできるというお話でした。
これだけは知っておきたい!!相続がおこった時のマメ知識
はじめに相続とは、人間が亡くなった瞬間より発生する「民法によって定められたルール」になります。亡くなった方と血縁関係にある方は「相続人」として相続開始の瞬間から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継するという定めになっております。相続なんて自分には関係ないと思っている方も、財産がたくさんあり相続について不安を感じたことがある方も、知っておくことで得する豆知識をご紹介させていただきます。
相続権のある人
・相続権のある人は誰?
相続権について法律では「相続人」と「相続分」に対して一定のルールを設けております。「相続人」とは「相続する権利がある人」のことであり、「相続分」とは「相続人が遺産を相続できる法律上の割合」のことを言います。相続人については、大きく分けて2つに分類されます。
1、遺言で指定された人
遺言書によって相続人を指定されている場合は、相続権が発生します。この場合「家族」や「身内」に限定されることはなく、遺言者が指定することができます。
2、法定相続人
配偶者+次のいづれか
①子供(先に死亡している場合は、その子供の孫)
②親(①に該当しない場合)
③兄弟姉妹(②において両親も先に死亡している場合)
※兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥姪
このように、亡くなった方よりも先に死亡している場合の次の相続人のことを「代襲相続人」と言います。
法定相続人は原則として、相続分については相続人間において「話し合って決める」ことが優先されます。話し合いでも決まらない場合においては「法定相続分」として、法律の定める割合で遺産を分配させることができます。(法定相続分での分配は後に持分などでトラブルになるケースが多いので注意が必要です。)
・法定相続分
(配偶者+子供)
配偶者は常に相続の対象となり、法定相続分割合では2分の1の割合を取得することになります。子供がいる場合は残りの(2分の1)x(子供の人数)=相続分となります。
(配偶者+両親)
配偶者の法定相続分割合は3分の2となり、両親は残る3分の1を双方で分割するため(6分の1)x両親2人=法定相続分となります。
(配偶者+兄弟姉妹)
亡くなった方の両親が先に亡くなっている場合は、配偶者の法定相続分割合は4分の3となり、残る(4分の1)x(兄弟姉妹の人数)=法定相続分となります。
相続財産の範囲
・財産になるものならないもの
「相続」では、プラスもマイナスも全部「相続財産」として引継ぐことになります。財産という言葉から連想するものは、預貯金や証券などの金銭価値や土地建物の不動産など、「プラスのイメージ」が強いですが、相続財産にあってはこればかりではありません。
(プラスの財産)
不動産(土地・建物)、現金、預貯金、有価証券、宝石、書画骨董など
(マイナスの財産)
借金、保証、未払いの最後の入院費など
遺産とは、亡くなった方が残した財産(権利と義務)のことを言います。そのため、必ずしも所有する「形ある金銭価値」(権利)ばかりではなく、未払金・滞納金や支払い義務のある請求書を始め、借金などの債務に対しては「支払わなければならない対価価値」(義務)が残っている場合もあり、これらを全て合わせた上で遺産の相続及び分割を検討する必要があります。
つまり「金目のものは欲しいけど借金はいらない」という限定はできないということになります。
借金相続
・知らなかったは通用しない!?
相続財産にマイナス財産つまり「借金」があったので放置しておいた。この場合「借金は相続する」ことになります。放っておくことで「相続を放棄」と勘違いしてしまいますが、法律では「相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の意思を申し出ない場合は相続するものとしてみなされてしまいます。相続放棄については、正式に「家庭裁判所」にたいいて「相続放棄」の手続きを行うことで初めて受理され、無事にじゅりがかんりょすることで「初めから相続人でなかった」ものとみなされます。このように法律の世界では「知らなかった」というのは認められず、法律というルールである以上は「O」か「X」の2択になってしまいます。
免許を持っていない人が車を運転して、赤信号を無視したとします。警察官が現行犯で取り締まりを行い、「免許を持っていないので知らなかった」「車の運転に免許が必要とは知らなかった」と証言しても、法律は「知らなかった」という行為に対しては「同情」してくれないことを覚えておきましょう。
相続税の心配
・相続税がよくわかない〜
相続税とは、亡くなられた方から相続などによって個人が財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金になります。相続税の申告については、「亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内」に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。必ずしも全員が該当するとも限らないため、基礎控除を参考に税理士の相談を利用しましょう。※税務に関する相談対応については「税理士法」において、税理士資格所有者のみが許されている行為になります。
・遺産にかかる基礎控除
相続税には基礎控除と呼ばれる下記のような「非課税枠」が設けられております。
3000万円+(600万円x法定相続人の数)※平成27年1月1日の税制改正
平成27年以前は基礎控除の枠が大きく5000万円以上の方が対象であったため、大幅な基礎控除額の減少によって納税義務者が増えたことは事実です。不動産や自社株などを所有している場合は「評価額」を知っておくことで、対策や相談を優位に行うことができます。
近年では税金対策という言葉も増えてきており、様々な形へ財産を有効活用することで、次世代へ最も適切な形で残すこともできるようになりました。
相続の手続きとは
・どんな書類が必要になるの?
相続の手続きには、どこから始めるにもまずは「相続手続き書類」が必要になり、これを揃えるのが結構大変です。具体的には次の書類が必要になります。
①遺言書 または相続人全員の署名実印押印のある遺産分割協議書
②戸籍一式(亡くなられた方の出生から死亡まで、相続人との関係がわかる戸籍一式)
③相続人全員の印鑑証明書(遺言書の場合は不要)
④相続する人の住民票 など
※行政・金融機関などによっては、規定の用紙やその他にも情報開示を求められる場合もあります。
一般的な手続きといえば、まずは「不動産の名義変更」があり、「金融機関の解約」「保険の解約及び保険金受取」などが眼前に立ちはだかります。これらの手続きすべてにおいて「相続手続き書類」は都度必要となり、必ず原本の提示を求められます。手続きによっては、止む得ず原本を郵送にて送る場合など、必ず返送してもらうことと、手続きに大変時間がかかることを覚えておきましょう。その書類がない間、他の手続きは一切前に進まないことになります。遺言書がある場合には省略できる書類もありますが、内容によりけりということもあり専門家に相談をする必要があります。特に手書きの遺言が発見された場合には、そのままでは効力を持たず「有効にする」作業を家庭裁判所に対しておこなう必要があります。家庭裁判所に提出する前に、遺言が有効なものであるかどうかを判断してもらうことで、無駄な費用は省けます。各種証明書類などについても難しい場合は、司法書士などの専門家に一度相談をしてみましょう。
【遺産相続】相続財産評価、現預金以外の評価について
相続で発生する相続財産はその評価について民事上と相続税法上で扱いが異なります。
遺族の間で相続財産を分ける遺産分けの場面では、各財産をどのように評価するかは遺族の間で決めれば良いことです。
公平な分配になるように、不動産などについては不動産業者に査定をお願いしてその価値を判定し、各人の取り分として分けることも可能です。
このようにして各相続財産を評価してまとめ、財産目録などとして作成します。
しかし相続事案では遺族間、相続人間での財産の扱いとは別に、相続税という税金の問題も出てきます。
税金は対国の関係ですので民事上の扱いとは全く異なる次元で処理しなければなりません。
以下では相続税の処理のための相続財産の評価について見ていきます。
■財産の評価法は国によって決められている
冒頭で述べたように、相続税の処理は民事上の扱いとは全く異なるので処理の方法が複雑になり、面倒さが増してしまいます。
相続財産の評価法が国によってあらかじめ決められており、これに則って相続財産を評価しなければならないのです。
例えば不動産などを民間の不動産業者に価値判断を委ねてしまうと、相続税額を不当に下げるためにわざと低評価をして、見返りにマージンを受け取るなどの行為が横行する恐れがあります。
こういった不正行為や、評価者による評価のずれなど不公平が発生することを防ぐためには国が一律の評価法を定め、全国どこでも同じ評価法によって相続財産を評価できるようにしなければなりません。
国は「財産評価基本通達」というルールを作り、相続財産の評価法について規定しています。
現金や預金といった金銭はそのままの額で評価するので問題は無いのですが、それ以外の不動産などは上記のルールに則って評価しなければなりません。
我が国の相続は遺産の中に占める不動産の割合が非常に大きいという特徴があるので、この評価について知っておく必要があります。
そして年数経過によって価値を大きく下げる家屋と違って、土地は基本的に価値が低下しないのでその価額が大きくなり、相続税の税負担に大きく影響してきます。
次の項で土地の評価についての基本から見ていきましょう。
■土地の評価法の基本
土地の評価法は大きく3つの種類があります。
主に宅地を評価するものとして路線価方式、郊外の土地について評価するための倍率方式、宅地以外を評価するための宅地比準方式です。
有名なのが路線価ですが、国が発表する路線価という土地評価の指標に土地の面積をかけて基本価を算定するものです。
路線価は国税庁が毎年7月中旬ころに発表しますが、評価時点は毎年1月1日時点の評価となります。
路線価は全国の税務署で閲覧することができますし、大きい図書館などにも設置されていることがあります。
また最近はインターネット上でも閲覧が可能になっています。
路線価は土地の評価についての基本的な指標となりますが、単純にこれに面積をかけて評価額が算出されるような簡単なものではありません。
様々な調整や補正が入り、複雑な計算を経なければならないため素人には難しく、場合によっては税理士やFPなどの専門家を利用することも必要になってきます。
それでは次の項から土地の評価手順について見ていきます。
■評価する単位を調べる
まず評価されるべき土地について、地目や利用の単位となっている区画を確認します。
土地の評価は原則として登記簿上の地目別に評価しますが、現況と登記上の地目が異なる場合は現況判断が優先されます。
また宅地は自宅用地や駐車場など、異なる目的でその土地が利用されますが、その利用の単位となっている区画ごとに評価しなければなりません。
登記簿上の一筆の土地ごとではなく、例えば自宅用地と駐車場用地の評価は別にしなければならないということです。
そこに路線価をかけていくのですが、路線価の読み取りが難しいので基本を押さえていきましょう。
■路線価の見かた
路線価は1㎡あたりの価額が千円単位の数字で表されています。
その数字が適用になる範囲は矢印で指定されています。
路線価図はベースに住所地図が用いられていますので、ご自分の所有する土地の場所は比較的容易に見つけることができます。
実際には上記の数字は横にアルファベットが付いていたり、丸や四角、三角などの記号に囲まれていることがあります。
丸や四角などの記号は地区区分を表しており、ビル街区や商業地区などの区分を表します。
この記号がないエリアは普通住宅地区を表します。
地区区分は後述する各種調整、補正の際に影響します。
アルファベットは借地権割合を表し、A~G(90%~30%)まであります。
借地権割合とはその土地の使用の自由度が落ちることになる貸地などとして使用している場合に評価に調整を加えるためのものです。
例えば他人に貸している土地だったり、アパートを立てて他人に利用させているような土地は100%自分が自由に利用できない分その評価を下げることができます。
評価を下げるというと不利になると勘違いする方がいますが、誰かに売るための評価ではなく相続税の算出のための評価ですから、評価を下げることができるということは税負担を減らすことができるということですので有利に働きます。
■自用地の評価法
自用地の評価については路線価に各種の調整を加え、これに地積をかけることで評価額が算出されます。
この「各種の調整」が非常に複雑で難しいため敬遠されますが以下で概要を見てみます。
・奥行価格補正率
土地はその面する道路からどのくらいの奥行きがあるかによって利用のしやすさが変わってきます。
奥行きが丁度よい土地の場合は補正が入りませんが、それより奥行きがあっても、逆になさすぎても利用のしやすさが落ちてしまうと考えて評価が下がるようにするのがこの補正です。
補正の度合いは上述した地区区分によっても異なってきます。
・側方路線影響加算率
正面道路の側方にも道路があり、二つの道路に面している土地は基本的に道路に面している範囲が大きいほどに評価を上げていきますが、道路が交わる角地の使いやすさについての評価もしなければなりません。
その為に入るのがこの補正で、使い勝手が悪くなる準角地(道路が交錯せず通り抜けできない角地)は評価が下がります。
・二方路線影響加算率
上記のような側方路線ではなく、土地の正面と裏面に道路がある場合の補正です。
・その他
他にも不整形な土地、がけ地にある土地、間口が狭い土地等についても対応する補正が入ります。
自用地については路線価にこのような補正作業を入れた後で地積をかけて評価額を算出します。
■貸宅地や借地権の評価
地主さんが誰かに貸している土地は借地権が設定されますが、この場合地主ではありながらもその使用は自由にならず強い制限が課されます。
その分評価を下げる必要がありますが、そのための方法が上述した借地権割合というものです。
地主側からみたその土地の評価は「自用地評価額×(1-借地権割合)」として評価されます。
反対に誰かから土地を借りて建物を建てているような場合は、土地に所有権こそなくても借地権という権利を有しています。
この権利自体も取引の対象になる価値を持っているのでその分を評価しなければなりません。
借地人側から見たその土地の評価額は「自用地評価額×借地権割合」として評価されます。
ただし、土地の使用のために金銭の授受が発生しない使用貸借関係の場合は地主の権利が強くなるので、地主側から見た評価は自用地評価額と同じくなり、借地人側からみた評価はゼロ評価となります。
使用貸借ではその賃借権はかなり弱く、無条件で相続人に引き継ぐこともできないので評価されないのです。
相続税の申告と納付について
相続税という税目が疎まれやすいのは税金を取られるという単純な理由もありますが、制度や仕組みが分かりにくいというのが大きな理由です。
相続税は「申告」と「納付」という二つの作業に分かれますが、その両方必要な人と申告のみが必要な人、両方不要な人に分かれます。
所得税と同じように自己申告制を取る相続税は、申告と納付の必要性も自分で調べて判断するしかありません。
法律上必要な申告や納付を怠れば相続税法違反となり金銭的なペナルティを課せられることもありますし、場合によっては懲役刑に処せられることもあります。
意図した脱税ではなくとも税務署にとっては追加徴税などで多く徴税できるチャンスですから容赦してくれません。
そこで今回は相続税の申告と納付について詳しく見ていくことにしましょう。
■相続税の申告と納付が不要な人とは
まずは申告と納付が「絶対的に必要のない人」を確認してみましょう。
これに該当すればあなたは相続税の申告も納税も不要です。
相続税には基礎控除という枠があり、相続財産がこの額以内であれば課税額は0になるので納税が不要なのはもちろん、申告自体も不要になります。
近年この基礎控除枠が縮小され、税負担が発生する人が増えるとされています。
現在の枠は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。
例えば法定相続人が三人であれば4800万円までの相続財産であれば相続税の申告も納付も不要です。
相続税の難しいところは遺産をそのままの額で評価できないという所にもあります。
自分で正味の遺産以外の色々な数字を足したり引いたりする計算を強いられます。
相続財産の数値化や債務控除など足し引きの計算方法については別の章を参照してくださいね。
■相続税の納税が不要でも申告の義務がある人とは
では次に、相続税の納税は必要ないけれど申告自体は必要な人とはどういう人か見ていきます。
相続税の処理ではまず相続財産を全て数字に直すことから始まります。
財産を数値化して課税標準を定めないと税率をかけて税額を算出できないからです。
そして計算上、厳密には遺産でないものも色々と相続財産に加えたり、逆に控除したりする作業が入ります。
そこから上記の基礎控除額をさらに控除し、残った額に一定の税率をかけて税額を算出します。
さらにここから税額控除といって一定の額を算出された税額から引くことができる場合もありますが、税額控除を適用した結果税金額が0以下になった場合でも申告だけは必要なこともあるので注意が必要です。
またそれ以外にも税負担を軽減する特例を使って税額を0以下にした場合は例え納める税金の額が0でも申告だけは必要になります。
申告を怠るとただの申告漏れ扱いとなってしまうので要注意です。
例えば多くの人が使える大きな減税措置である「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」などを利用した場合は例え税額が0になったとしても申告書の提出だけは必要になります。
■相続税の申告書の提出先は
相続税の申告先は原則として被相続人の生前の住所を管轄する税務署になります。
相続税は被相続人ではなく相続人に対してかけられるため、自分の住所に最寄りの税務署と勘違いする人が多いです。
遠方の実家で相続が発生した時にはその地元の税務署に対して申告しなければなりません。
例外として、被相続人が外国で死亡した場合の取扱いがあります。
アジア圏など生活費が安い海外で老後を過ごす方も増えていますから、この場合は取扱いが異なります。
まず、被相続人が海外で亡くなっても、その相続人が日本国内に居住していれば「居住無制限納税義務者」という扱いになります。
この場合は当該者の住所地の管轄税務署が申告先となります。
また、「非居住無制限納税義務者」という扱いもあり、相続発生時に日本国籍を有しておりながら日本国内には住所を有していない者などは住所地管轄がないので、改めて納税地を定めて申告しなければならないことになっています。
詳しくはこちらで確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138_qa.htm
■相続税の納税が必要な人とは
相続税には様々な控除措置や特例が用意されていて、これらを利用することで計算上の税負担が0になる場合があります。
基本的な債務控除や基礎控除は誰でも使えますが、特例などは個々人によって使える人とそうでない人がいます。
こうした控除や特例を使って計算をしてもなお税負担が生じた場合には申告だけでなく納税も必要になります。
申告と納税の期限は同一で、相続発生の翌日から10か月以内となっています。
税の納付は税務署でも行えますが金融機関などでも可能です。
この期限を逸すると延滞税などペナルティが発生しますので注意してください。
納税は金銭で一括納付が必要ですが、遺産のほとんどが不動産などの場合は納税資金を用意することが難しいこともよくあります。
どうしても期限までに納付が難しい場合は延納や物納が認められることもあります。
■延納と物納の制度
延納とは分割払いの方法を用いて納税期限を伸長しながら少しずつ納める方法です。
物納は文字通り金銭以外の一定の財産でもって納税する方法をいいます。
どちらも必ず認められるというわけではなく、事情を説明してどうしても納税が難しいと税務署が判断した場合に限り認められるものです。
延納が認められるには納付額が10万円を超えること、一定の担保を提供することなど一定の条件を満たさなければなりません。
担保に供することが認められるのは国債や地方債、社債、土地や建物などに限られます。
延納制度を使うには利子税を納めることも要求されます。
相続財産に占める不動産の割合が大きいほど、納税資金を用意することが難しいと判断されて利子率や最長延納年数などの面で有利になる仕組みです。
ちなみに利子税は年一回の元金均等払によって納めます。
延納と物納には優先順位があり、最初から物納を検討することはできません。
まずは延納を検討し、それもダメな場合にのみ物納が検討されます。
物納できるのは被相続人が残した相続財産に限られ、相続人固有の財産は利用できません。
また国による利用を考えて、国内に存する財産しか利用できません。
物納に利用できるものは限られ、それらにも優先順位が設定されています。
まずは国債や地方債があれば最優先で利用されます。
それがなければ次は不動産や船舶、それもなければ社債や株式など、されにそれもない場合には動産も利用可能です。
ただし質権や抵当権の目的となっているものは利用できません。
物納では利用されるその物品をどうやって評価するかが問題となります。
金銭価値を判断しないと納税にならないからです。
これを「収納価額」といいますが、収納価額は相続が発生した際の相続税評価額となります。
相続税評価額というのは金銭以外のものについて、相続税の税額計算の為にその価値について判定したものです。
例えば不動産であれば、単に不動産屋の査定額が相続税評価額となるわけではありません。
国が定めた一定の評価法に従って算出されるもので、全国どこでも同じ基準で判断ができるように国がその評価法を定めています。
「財産評価基本通達」といって、相続税の計算の為に遺産を数値化するためのルールとして決められています。
これによって地域によって財産の評価にズレが生じて不公平感がでることなどを防ぐことができます。
相続関連手続きスケジュール
相続事案の怖いところは前触れなしに訪れることが多いということです。
遺族となり得る方に医師が「いよいよ準備を」と病床で促すこともあるでしょうが、それも当日や前日であることが多いですね。
子どもが生まれる場合は出産時期などをあらかじめ予測できるので諸準備の対応がしやすいですが、人の死の場面は予測が難しく、精神的にも動揺してしまってしばらくは的確な行動がとれないこともあります。
そこで平素から相続がいざ起きた時にはどのような行動が必要になるのかを把握しておくことが大切になります。
今回は相続に関係する手続きと、その手続きにあたってどんな行動が必要になるのか考えてみましょう。
■7日以内には役所への死亡届を
相続は人が死亡することですからそのご遺体の処理を適切に行わなければなりません。
病院で死亡した場合でも自宅で看取った場合でも、必ず医師による死亡診断が必要です。
医師は死亡を確認すると死亡診断書を作成してくれます。
この死亡診断書は死亡届とセットになっており、半分を死亡診断書として医師が記入し、もう半分を遺族が必要事項を記入して地元の市区町村役場に死亡届として提出します。
すると役所からは火葬許可証が発行されますので、火葬場でご遺体の焼却ができるようになります。
火葬場では埋葬許可証が発行され、これをもって無事に埋葬ができますので、ご遺体の処理としては一件落着となります。
■3か月後に迫る限定承認または相続放棄の準備
一方、財産関係の問題は別に動かなければなりません。
相続の放棄や限定承認をするためには被相続人の死亡(相続発生)から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
相続の放棄は被相続人に借金など負債の方が多く、そのまま相続してしまうと相続人が借金の返済に追われることになる場合に「相続人となりません。なにも承継しません」ということです。
限定承認はプラスの財産の範囲でのみ借金などマイナスの財産の負担をまかなうことができるもので、放棄も限定承認も正しく手続きをしないと、単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全て承継しなければなりません。
ですから隠れ借金がよくある自営業の方が亡くなった時は特に注意が必要です。
つまり単純承認して全ての遺産を承継しても問題ないのかどうかというのは自分で遺産の内容を詳しく調べてみないと分からないということです。
そのため財産関連の情報を自ら採集していく作業が必要になります。
また遺産の取り分は相続人の数にも影響されるので相続人の確定作業も同時進行で進めます。
遺産の情報は被相続人が残してくれる遺言書に多くの情報が書かれているのでまずは遺言書を捜索します。
被相続人が自筆で作成した自筆証書遺言は公正証書遺言と違って、家庭裁判所で偽造などの跡がないかどうかを調べる「検認」という作業が必要ですから勝手に開封せず、裁判所に持ち込んで手続きを取らなければなりません。
同時進行で相続人の調査も必要です。
被相続人の戸籍を辿り、その出生までさかのぼって関係する血縁者を探します。
引越しが多い方が亡くなった場合は複数の役所と何度かやり取りして手間と時間をかける必要が生じることもあります。
この作業は行政書士などの専門家に代行を頼むことができます。
戸籍情報の読み取りは素人では難しいこともあるので専門家を頼るのが面倒がなくて済みます。
特に電子化前の古い戸籍は筆跡の判別に非常に苦労することもあります。
遺産の種類や額の検証も並行して行います。
遺言書に書かれた現預金や不動産などの遺産だけでなく、借金についても調査して、それらを「財産目録」として一覧表にまとめます。
借金については遺言書に記載がないことも往々にしてあるので、督促状や支払通知書などを見つけたらその会社(金融機関など)に連絡を取って債務の状況を確認しなければなりません。
事業を行っていた方が亡くなった場合はこの債務調査を特に念入りにした方が良いです。
難しい場合は専門家に依頼すれば代行してくれます。
さてこのように相続人の人数を確定し、また遺産のプラスマイナスを確定すると自分がどれだけの遺産を承継できるのかが分かります。
ここまでやってようやく「承継しても問題ないか」が判別します。
問題がなければそのまま単純承認でOKですが、負債の方が大きくなる場合は相続放棄の手続きを取ります。
また何らかの要因で負債額の詳細が判別できない場合もあるでしょう。
その場合はしっかりと調査したうえで財産目録などの説明資料をそろえ、責任がプラスの財産の範囲に限定される限定承認の手続きをとることもできます。
ただしこの限定承認は実際の手続きがひどく煩雑で時間がかかることや、相続人全員の合意で行う必要があることから手続件数としては多くないのが実情です。
■4か月後に迫る準確定申告の準備
準確定申告とは被相続人のその年の収入について、相続人が代わって行う確定申告のことです。
たまに、相続税の確定申告と勘違いする方がいますが、これはあくまでも「被相続人の分の」収入について申告と納税を代わって行う作業になります。
年金だけで生活している方が亡くなった場合は特に手続きが要らないこともありますが、その場合でも年金の額が400万円を超える高額受給者である場合や、その他の収入がある場合は多くのケースで確定申告が必要です。
特に事業を行っていた方の場合はその事業に関係する帳簿などを採集して、経費処理なども行ったうえで税務署に対して申告と納税が必要です。
相続発生後4か月というのは余裕がありそうですぐに来てしまいますから速やかに準備に着手しましょう。
経理の担当者がいれば心強いですが、個人事業で従業員がいない場合などは事業所内を捜索して仕入れ表や納品書など関係書面の収集が必要になってきます。
経費処理などの計算が難しい場合税理士が代行してくれますので適宜利用しましょう。
■10か月後に迫る相続税の申告と納税
こちらが相続人の方自体にかかる相続税という税目の処理過程です。
相続税には基礎控除の枠があり、これ以下の遺産額であれば相続税はかかりません。
問題となるのはその遺産の評価額です。
相続税は課税対象となる財産に一定の税率をかけて税額を算出しなければなりません。
現金や預金はそのままの数字で良いのですが、不動産はどうでしょう?あるいは証券類は?
こういった財産は国が定める「財産評価基本通達」に則って一定の規則で評価を行い、遺産を数字化しなければならないのです。
従って被相続人が残してくれた遺産は全て相続税の計算の為に財産評価を行い数字化するという作業が必要になります。
素人では難しい場合は税理士に依頼しましょう。
また相続税は複数相続人がいる場合、個々人で計算して申告納税しなければなりません。
ですから自分がどれだけの財産を承継するのかといったことを確定しなければなりません。
そのためには他の相続人と協議を行ってその合意を書面化しておく必要があります。
遺言書があってその通りにする場合や相続人が一人だけの場合など遺産分割協議書が必要ないケースもありますが、複数相続人がいるケースでは多くの場合後でトラブルが生じないように合意書面として遺産分割協議書の作成を行います。
不動産については名義の変更が必要で、その登記の際には登記官が「確かにこの者に権利がある」と分かる資料としてこの遺産分割協議書の提出を求められることもあります。
このようにして、相続財産を数字化し、各相続人の取り分を確定すると、実際に自分がどの財産をどれくらい承継するのかが目で見て分かるようになります。
相続税の申告は相続開始から10か月以内にこれらの情報を基に税務署に対して申告納税手続きを行いますが、その申告先は被相続人が生前住んでいた住所を管轄する税務署です。
間違えやすいですが相続人の住所管轄ではないので注意してください。
今からできる相続対策!生前贈与の活用法
近頃、何かと話題の「相続対策」。相続税の非課税枠である基礎控除額が縮小され、課税対象となる方が増える、とされているためですね。
特別な富裕層にだけ関係のあるものではなく、都心にマイホームを持っているような家庭であれば、充分、相続税が発生する可能性はあります。
しかし、「じゃあ相続対策として、何をしておけばいいのか」というのは中々分かりづらいもの。今回は相続対策の代表とも言える、生前贈与の活用法についてポイントを解説します。
生前贈与とは。贈与税とは。相続税との関連は。考え方を理解しましょう。
生前贈与とは、読んで字のごとく、「生きているうちに財産を親から子などへあげること」です。
行為自体は簡単なものですが、自由に何の制約も無く、あげる、もらう、ができるのであれば、こんなにも相続対策などが話題になることはありません。
財産をもらった人に対して、「贈与税」という税金が課されます。「親から子へ財産を渡して、なぜ税金がかかるんだ」という感覚を持たれるのも分かります。
しかし、この制度を設けておかなければ、「相続税」というルールが成り立ちません。
生きているうちにどんどん財産を渡して、亡くなる際には非課税枠以下の財産だけ、としてしまうためですね。そのため、国は贈与という行為にも税金を課すことにより、相続税の課税を補完しているのです。
年間110万円までの贈与なら贈与税はかからない
一年間の間(その年の1月~12月の間)に贈与を受けた金額が110万円以内であるならば、贈与税はかかりません。
確定申告も不要です。暦年贈与の非課税枠とか、基礎控除枠、年110万の非課税枠、という呼称を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
ただし、この「年110万円」というのは、「贈与を受ける人一人当たり」の非課税枠ですので注意が必要です。つまり、父と母、それぞれから110万円ずつ子に贈与する。
これはダメです。贈与を受ける子は、110万円+110万円=220万円の贈与を受けているためですね。
贈与を成立させるには双方の認識が必要
「年110万円以内の贈与なら、贈与税はかからないんだな。よし、それじゃあ子に孫に、ひ孫に、みんなに毎年110万円ずつ渡していこう!」
はい、これもダメです。贈与という行為は、お互いに「あげました、もらいました」の認識があり、もらった側が、それを自ら管理し、自由に使えてこそ成立するものだからです。
小さい子供が、110万円を貰ったという認識があるでしょうか。まず、小さい子供に直接渡したりしませんよね。
子供名義の預金口座を作って、そこに入れておく、というのが通常かと思います。そして当然、子供にそれを自由に使わせたりはしないはずです。
「いや、直接渡したよ」「自由に使わせたよ」とかいう問題ではなく、未成年に対して大金を贈与する、という時点で、その行為そのものが調査の際に指摘される可能性があります。「毎年の常識的な額のお年玉を、子供名義の預金で積み立てていた」というのとは、訳が違います。
では、成人した子や孫に、年110万円ずつ渡していこう、としたときにも、注意が必要です。
上記の通り、単純に子や孫の預金口座を作って、そこにお金を移しているだけでは、「名義預金」に他ならず、親の死亡時には、相続財産として扱われ、相続税の課税対象となりかねません。
預金口座は、子や孫が自ら印鑑や通帳を管理し、いつでも引き出しができる状態にさせておくとともに、贈与契約書を毎年作成し、贈与が成立している証拠を残しておきましょう。
教育資金贈与の一括贈与特例を活用しよう
孫の入学祝いや、入学金そのものを祖父母が出す、ということは一般的なことであり、それが常識的な範囲である限り、贈与税が課税されることはありません。
「じゃあ別に特例じゃないじゃないか」と、この制度の概要を聞いて最初に思いがちなのですが、「一括で」教育資金の贈与ができる、という点が大きなメリットであり、特例なのです。
この制度は、祖父母から孫へ、というように直系尊属からの贈与で、教育に充てるための資金であれば、1,500万円までであれば贈与税が非課税となる制度です。
つまり、現在5歳の孫に、これから先、中学、高校、大学入学の資金として、1,500万円以内であれば「今、一括で」しかも非課税で渡すことができるということですね。これは大きなメリットです。
具体例を見てみましょう。現在1億円の財産を持っている祖父が、2人の孫に、これから先の教育資金として、1,500万円ずつ、計3,000万円を渡すとします。
その状態で相続を迎えると、相続財産は1億円-3,000万円=7,000万円です。この制度を利用しなかった場合には、相続財産は1億円のままですので、相続税の課税対象である相続財産が、3,000万円も違ってきますね。
それに伴い税金の額も大きく変わってくるので、この制度のメリットをお分かり頂けるかと思います。
この制度を利用する上で気をつけるべきポイントは、まず「教育に関する資金であること」。
教育に関する資金とは、どこまでを指すのでしょうか。これについては、①学校等へ直接支払われる入学金や授業料、②学校等以外の教育に関する資金で大別されており、①は小学校~大学、②は学習塾や、スポーツの習い事というイメージで捉えて頂ければ結構です。
そして②の用途での教育資金は、500万円までと上限が決まっています。
無尽蔵に非課税目的で習い事をさせることに歯止めを掛けているわけですが、500万円もあれば、一般的には成人するまでに充分な習い事ができますよね。
そしてもう一つのポイントは、「その贈与を受ける者が、30歳になるまでに使い切ること」です。
30歳を超えてから資格を取り始めることなどもあるでしょうが、その資金に充てることはできません。30歳の時点で使い切っていない場合には、その残額に対して贈与税が課されてしまいますので注意が必要です。
贈与税の配偶者控除 ~通称:おしどり贈与~ を活用しよう
贈与税の配偶者控除(以下、おしどり贈与)とは、夫婦間でのマイホームの贈与、又はマイホームの購入資金を贈与した場合に、2,000万円までは贈与税が非課税となる制度です。
長年連れ添った妻に対し、自宅の持分を分けることについて、妻の内助の功を考慮した制度ですが、妻から夫への贈与も可能です。適用には以下の要件を全て満たす必要があります。
(適用要件)
- 入籍してから20年以上経過していること
内縁の妻等、正式な婚姻関係でない、いわゆる事実婚の場合には認められません。
- 居住用不動産そのものか、その取得のための金銭であること
マイホームに関係のない財産はダメです。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること
もともと住んでいる自宅の贈与であれば関係ないですね。
- 過去にこの制度を利用したことがないこと
一生に一度の適用です。
- 贈与税の確定申告を行うこと
贈与税が発生しなくても、特例を受けるためには確定申告が必要です。
実はこの「おしどり贈与」については、税制上のメリットはそこまで大きいとは言えない、と言われることがあります。
なぜならば、相続が発生した際に、配偶者に対しては1億6千万円までの財産は相続税が非課税であるためです。
つまり、「生前に配偶者に渡しても、渡さなくても、配偶者に対しては相続税がかからない」というケースが殆どかと思います。
そのため、「配偶者への感謝の意」を表すものとして、マイホームの名義を一部付け替える、共有名義にする、という意義の方が大きいのかもしれません。
結婚・子育て資金の一括贈与特例を活用しよう
上述の教育資金贈与と同様に、結婚・子育て資金についても、両親や祖父母が幾らか援助する、というのは一般的なことであるため、教育資金贈与と同様の特例があります。
こちらの制度は、1,000万円が限度(結婚資金については300万円が限度)で、贈与を受ける子や孫は、20歳以上50歳未満であること、という条件があります。
また、制度を利用する上では「結婚資金」「子育て資金」とは何を指すのか?ということを理解しておく必要があります。
「結婚資金」とは、「結婚式や披露宴で通常かかる費用」というイメージで概ねOKです。
会場費、衣装代、引き出物代などですね。婚約指輪代や結婚指輪代は対象外です。また新婚旅行代も対象外です。
「え~!指輪代や旅行代、親に援助してもらうつもりだったのに・・・」という方もいらっしゃると思いますが、大丈夫です。
お忘れではないですか?年110万円の非課税枠を・・・。この特例の対象外のものについても、年110万円の基礎控除枠で結果的にカバーされているケースが大半ですので、大きく超えていないかのみ確認しておきましょう。
「子育て資金」とは、「妊娠・出産に係る費用」「子の医療費」「幼稚園の入園費用」というイメージで概ねOKです。
ただし、妊娠の治療や出産を、本人の希望で遠隔地や海外で行いたい場合の渡航費など、一般的に必須とは捉えられないものに係る費用は対象外です。
相続対策としての生前贈与にも様々な制度がありますが、まず基本は年間110万円以内の基礎控除です。
こちらを確実に行いながら、各種の特例を併用していくと、より有効に生前贈与を進めることができます。
各種の特例には細かい適用要件が設けられており、実は要件を満たしておらず、多額の贈与税が掛かってしまうリスクもあるため、税理士等の専門家に相談の上、慎重に進められることをおすすめします。
子なし家庭が注意すべき相続の注意点6点
近年、若い世代でもじわじわと子供がいない世帯が増えていますね。
自身の相続を考える世代の方々の中にも様々な理由で子供のいないご家庭もあります。
遺言講座や高齢者向けのファイナンシャルプランニングサービスでは夫婦二人と子どもが1人~2人程度のケースを想定して解説されることがほとんどですが、相続というものに視点を絞った場合、子どもがいる場合といない場合とでは対策の立て方が異なります。
今回は一つの悲しい実例を挙げながら、これを軸に子供のいないご家庭で相続対策を考える際の注意点を見ていきましょう。
■配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースは警戒度MAX!
我が国の法制度は相続に関しては民法上で基本的な決め事が設定されています。
どんなケースで誰にどれだけの財産が相続として承継されるのかといった基本事項が決められているわけです。
夫婦に子供がいない場合誰が相続人になるのかもこの中で決められていて、場合によっては何も対策をしないと長年連れ添った配偶者が住居を追われる可能性も出てきます。
ここで実際に起きた最悪の事例を一つご紹介しましょう。
旦那さんは奥さんと一緒に暮しておりましたが子どもがいませんでした。
彼も75歳と高齢で、親はすでに亡くなっています。
旦那さんは自分には子どもがいないので自分の死後は当然に奥さんが全て相続するものだと思い、特に対策などは行っていませんでした。
そして旦那さんの死後にはわずかな現預金と住居の一軒家だけが残されました。
奥さんはその家で慎ましく暮らしていくつもりだったのですが、ここに旦那さんのお姉さん(Aさんとします)が登場します。
奥さんとAさんは普段は付き合いはありません。
一般的に自分の配偶者とは当然仲が良くても、その兄弟姉妹と仲良くするというケースは稀と言って良いでしょうね。
奥さんもそうだったわけですが、ここでAさんが自分の遺産の取り分を主張してきました。
奥さんはビックリしましたが、喧嘩もしたくないので弁護士に相談して相応の取り分を分けて上げようと思いました。
しかし現預金がわずかなため家を売るしかありません。
家も古いため高額では売れず投げ売りになりました。
奥さんは次の住居を探しましたが高齢者には孤独死や自殺、未納のリスクがつきまとうためなかなか貸し手が見つかりません。
理由がどうであれ、人が死亡するとそのアパートなりマンションなりの価値が激減してしまうからです。
奥さんは何とか行政の助力も得てアパートを見つけることが出来ましたがほとほと疲れ果ててしまい、心労で体を壊してしまったそうです。
相続事案を扱う弁護士や税理士の間ではあたりまえのこととして語られる逸話です。
ですから配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になることが想定される場合、必ず早めに遺言書の準備をしておくようにアドバイスします。
この事例では内容は至極シンプル、「全ての財産を妻の〇〇に相続させる」という趣旨の内容にすれば何も問題は起こらなかったのです。
なぜこのようなことが起こるのか、次の項で見ていきます。
■遺言書の内容は原則として民法の定めよりも優先する!
先ほどの事例は故人(被相続人)の兄弟姉妹も法律上の相続人として相続分の主張ができることを知らず、対策を怠っていたためです。
民法が定める相続人は次の通りです。
配偶者:生存していれば必ず相続人となる
第一順位:子
第二順位:被相続人の直系尊属(親や祖父母など)
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
まず配偶者は生きていれば必ず相続人となります。
ですから上の実例でも奥さんは相続人になることができました。
しかし配偶者以外にも、優先優位が高い順に生存していれば相続人になれるのです。
実例では第一順位の子と第二順位の親もいません。
この場合親のさらに上の世代、祖父母が生きていれば相続人となりますが、高齢ですでに死去されていました。
残ったのが第三順位の兄弟姉妹、実例では姉のAさんです。
つまりこのケースでは奥さんと兄弟姉妹のAさんが相続人として正当な権利者となり、相続分を主張できるということになります。
この例では奥さんは全遺産の4分の3、Aさんは4分の1を主張できます。
現預金が多ければ現金で支払うこともできるでしょうが、日本の相続では不動産が多くを占めるのが普通で資金を準備できないことも多いのです。
そのため不動産の現金化が必要になるのですが、往々にして満足のいく売却額とはなりません。
もしこの時、旦那さんが「全ての財産を奥さんに相続させる」旨の遺言書を作っていたらどうでしょう。
実はこの場合、原則として民法の定めよりも遺言書の方が優先されるので、Aさんは取り分の主張をすることができず、奥さんは全ての財産を貰い受けることができます。
ですから住み慣れた自宅を追われることはなかったのです。
これは完全に旦那さんの理解不足、対策不足でした。
ちなみに、遺言書が無い場合の法定の取り分(法定相続分)はケースごとに以下のようになります。
もし自分が遺言書を準備しないで死亡したら、誰にどれだけの遺産が渡ることになるのか想像してみましょう。
・配偶者と子が相続人となるケース
配偶者と子が2分の1ずつ。子が複数の場合は均等に分ける
・配偶者と直系尊属が相続人となるケース
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
・配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケース
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
これを見ると、法律は血縁関係よりも実生活で伴侶となった配偶者を優遇し、次いで血縁が濃く精神的な繋がりが強い順に優先されているのが分かりますね。
ただしこの規定は遺言書が無い場合を想定して法が準備しているものですから、先ほどお話したように遺言書がある場合は原則として遺言の内容が優先になります。
従って例えば配偶者には何も残さず、姉のAさんに全ての財産を相続させる旨の記載があればそれが優先されることになります。
この遺言の内容を覆したい時は、相続人などの権利者が全員合意の元で話し合って自由な取り分を決めることができます。
冒頭の実例では、奥さんと姉のAさんが双方の合意の元で「奥さんだけが相続する」旨の取決めをすれば奥さんは救われていましたが、情や繋がりが薄い相手にそこまで譲歩することは期待できません。
従ってやはり遺言書の準備は非常に重要ということになるのです。
■遺留分にも注意!
上の項で、例えば姉のAさんに全財産を相続させる遺言にすることも可能とお話しました。
確かにそれは可能です。
しかし法律は遺言書でも覆すことができない、ある規定を設けています。
それは「遺留分」という権利です。
遺留分は一定の相続人に最低限の取り分の主張を認めたものです。
ですから例え遺言書で遺留分を無視した分配(『遺留分を侵害する』といいます)内容にしたとしても、遺留分を持つ権利者が主張すれば、最低限の遺留分の取り分を主張できることになります。
この点、遺留分はあくまで「権利」であって当事者が主張しなければ遺留分の権利は行使できません。
ですから遺言で誰かの遺留分が侵害されていても、その人が納得している場合や、何らかの見返りを受けることで遺留分を主張しなければ遺言書の内容が実現できます。
もしこの権利を主張する場合は「遺留分減殺請求」という形で主張することになります。
遺留分の権利者は配偶者と子及び直系尊属だけです。
そしてその遺留分は次の通りです。
・直系尊属だけが相続人となるケース
法定相続分の3分の1
・上記以外のケース
法定相続分の2分の1
上記の通り、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
ですから奥さんが住居から追い出された冒頭の実例で、旦那さんが「妻に全財産を承継させる」旨の遺言書を作っていたら、姉のAさんは遺留分の権利主張もできないので、奥さんは遺言書によって完全に守られることになります。
逆にもし、「姉のAに全財産を相続させる」旨の遺言内容だった場合には、奥さんは法定相続分の2分の1の遺留分の権利を主張して、姉のAさんに対して遺留分減殺請求をかけることによって遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求は、その請求の証拠が残るように内容証明郵便などで行うようにします。
なお、この「遺留分」の規定ができた背景には、親族や情が通った配偶者などが相続の場面で理不尽な扱いを受けないようにという配慮があります。
例えば、家族を顧みず遊びにほうけて外で作った愛人などに全財産を譲るなどという事例も無いわけではありません。
実際似たような事例は今でも見聞きしますよね。
これでは家族が余りにもかわいそうだということで、法律によって一定の者に遺留分の権利を保証したのです。
■代襲相続にも気を配ること!
冒頭の実例で、もし姉のAさんも亡くなっていて、他に兄弟姉妹もいなければどうだったでしょうか。
第三順位の兄弟姉妹までいないことになるので、残った奥さんだけが相続人となって安泰でしょうか。
実はまだ安心できません。
民法には「代襲相続」という規定があり、一定の相続権利者が被相続人の死亡前にすでに死亡していた場合、その下の世代が上の世代の相続権を受け継ぐことができることになっています。
冒頭の実例では、姉のAさんが亡くなっていたとしても、Aさんに子があれば(仮にBとします)、BがAさんに代わって相続人(代襲相続人)となります。
ですから遺言書がなければやはり奥さんはBさんに法定相続分の取り分を持っていかれることになります(Bさんが任意で遺産を受け取らないことはできます)
また代襲相続人は被代襲者(死亡していなければ相続人となっていた者)の権利をそのまま引き継ぎます。
そのため遺留分の権利がある者を代襲した場合は代襲者も遺留分の権利を行使できますが、元々遺留分の無い被相続人の兄弟姉妹の代襲者は遺留分の権利はありません。
今回の事例では姉のAさんが亡くなっていてその子Bが代襲したとしても、「全財産を妻に相続させる」旨の遺言があれば遺留分の権利も行使できませんから奥さんは完全に守られ、安住の住処で暮らすことができます。
ちなみに、代襲相続が認められるのは子と兄弟姉妹のみで、直系尊属には認められません。
また子の代襲は下の世代が生きていれば永久に認められますが、兄弟姉妹の代襲は1世代のみ、つまり当該兄弟姉妹の子までしか認められません。
■妻以外の女性の子も相続人になる!
もう一つ盲点になることをお話します。
前述した通り、相続人になり得るのは配偶者の他に子、直系尊属、兄弟姉妹がいます。
そして子と兄弟姉妹には一定の代襲相続が認められることもお話しました。
このなかで「子」とは、何も直前まで婚姻関係にあった配偶者との子に限られません。
つまり前妻の子も第一順位の相続人と成り得るのです。
実際の事案で隠し子が発覚して大問題になるのはこのためです。
結婚を何度か繰り返している方が亡くなった場合、以前の配偶者との間に設けた子は立派な相続人です。
今回の事例では前妻は出てきませんでしたが、もし旦那さんに前妻がいて子(仮にCとします)がいる場合は姉のAさんではなく、優先順位の高い子であるCが奥さんと共に相続人となります。
この場合旦那さんの姉Aさんよりもさらに情関係がないCは容赦なく奥さんに自分の取り分を請求してくることでしょう。
ただしこの場合もやはり遺言書の準備があれば奥さんを守ることができるのは変わりありません。
とにもかくにも、遺言の準備が大切なことがお分かりいただけたでしょうか?
遺言はどんな場合でも準備するに越したことはありませんが、子どもがいないケースでは特にその重要性が増すのです。
■専門家に相談する場合の注意点
登場人物が増えるほどに関係は複雑になり、誰がどんな権利を持つことになるのか分かりにくくなります。
これから自分の人生の終わりの準備をしようと思っている方はぜひ万全の準備と対策を心がけたいものです。
自分だけで処理しようとすると、知識不足や情報不足から思わぬ落とし穴にはまってしまう危険があるので、専門家へ相談することも有効です。
その時には権利関係を一つ一つ丁寧に説明する必要があり、隠し子などがいる場合でも正確に伝えなければ正しいアドバイスを受けることができず、かえってマズイことになってしまう公算が大ですから正直に話すようにしましょう。
親族関係図などを作っていくと呑み込みが早くなるので相談を受ける側としてはかなり助かります。
肝心の専門家選びとしては弁護士、、税理士、司法書士、などが適応になりますが、いずれも相続問題に明るい人材を選ぶようにしましょう。
各専門家とも実際は取扱分野が広く、相続関係には明るくなかったりします。
不動産を相続した時にするべき4つの手続き
相続が発生すると、故人が生前に所有していた財産が相続財産として相続人等の権利者に承継されることになります。
我が国の相続事情は相続財産に占める不動産の割合が高いという特徴があります。
特に地方では持ち家率も高く、老齢の親が亡くなった場合にその住処が相続承継の対象になります。
また不動産は相続税の対策としても有効で、現預金よりも相続税評価額が低くなるため、税負担を減らすために現預金を積極的に不動産に変える(購入する)ことが多いことも理由の一つです。
そのため日本国内の相続事案ではほとんどの場合不動産の承継が行われることになります。
今回は不動産を相続した場合の手続きや注意事項について解説していきます。
■手続き1:遺言書の検認手続きまたは検索・照会請求
近年、「終活」や「墓じまい」などがブームになっていますが、高齢化が進む現代では自身の命の終焉に向けて必要な準備をするという意識が高まっているのが分かりますね。
元々このようなブームに関わらず、わが国には「遺言」という法的なルールがあり、自分の生前の財産の分配などについて後の世代に引き継ぐ手段として活用されてきました。
遺言の内容を書面に記したものが「遺言書」となるわけですが、相続争いを防ぐためにも有効であることが広く浸透していますので多くの事例で遺言書が作成されます。
この遺言書は扱いに注意しなければならないことをご存知でしょうか?
あなたが故人の家族で相続人となる場合、タンスの引き出しから遺言書が出てくるかもしれませんね。
よくテレビドラマなどでは親族が一堂に会して故人の遺言書を開封する場面がありますが、これをしてしまうと法律違反になってしまいます。
「過料」といって一種の罰金を取られてしまうこともあるので注意が必要です。
タンスなどにしまわれた遺言書は「自筆証書遺言」といって、故人が自筆で作成して保管していたものです。
自筆証書遺言は偽造や変造の可能性があるため、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
検認は裁判所が関与することで全ての相続権利者に対してその通知を行い、相続が起きたことを知らせる意味もあります。
そのため相続人を確定させなければならないので、故人(被相続人)の方の出生時から死亡時までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
詳しくはこちらで確認できます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/
ただし遺言書は公証人が関与して作成される「公正証書遺言」で作られることもあります。
この場合は検認作業は必要ありません。
公証人とは裁判官や検察官、弁護士など法律に関わる仕事を長年してきた一定の者が法務大臣によって任命される公務員です。
法律の専門家が関与して作成され、公証役場に原本が保管されているので偽造や変造の心配がないので検認をしなくてもよいことになっています。
故人が生前に公正証書遺言を作成したことを話している場合は最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。(遺言書の検索・照会請求といいます)
また正本(写しのようなもの)の交付がされているはずですから、これを発見した場合も当該公証役場に問い合わせが必要です。
■手続き2:相続を原因とする所有権移転登記
我が国では不動産の権利について明確にするために「登記」というシステムが取られています。
土地や家屋などの不動産に所有権や抵当権などの権利がある者は、これを登記システムに反映させることでその権利を明確にし、他者による権利侵害を防ぐことができます。
登記システムは法務局が管理しており、登記手続きも法務局で行います。
相続によって不動産を取得した場合は相続を原因とする所有権移転登記を行うことによって自分の権利を第三者に有効に主張することができるようになります。
この登記は法律上は必ずしなければならないものではなく、その期限も特に定められていないため先延ばしにしたり失念するケースも散見されますが、他者による権利侵害やいざその不動産を売却しようとするときに上手くいかなくなったりと、色々と不具合が出る危険性が非常に高いので登記手続きは必ず行うようにしてください。
所有権移転登記はよく「名義変更手続き」などとして紹介されることがありますがこれは正確ではありません。
名義変更というのは実際は本来の所有者の住所の変更登記のことなので別の手続きになるのですが、イメージ先行で所有権移転登記のこととして呼称されることもあります。
また所有権移転登記には売買を原因としたものと相続を原因としたものがあり、それぞれ手数料の税率が異なります。
相続を原因とするものはその不動産の固定資産税評価額の0.4%の税率がかかり、手数料として登録免許税という税金の形で納付することになります。
登記作業に必要になる書類等はケースによって異なります。
有効な遺言書がありそれに従って不動産の権利を承継する場合は比較的手間がかかりませんが、そうでない場合には法務局にその不動産の権利を誰が正当に取得したのかを説明、証明するために色々な資料が必要になることがあります。
まず複数相続人同士で自由に不動産の権利を定めた場合は、その約束事を確認できる遺産分割協議書が必要です。
またその協議に参加した者が正当な権利を有する者であることを証明するために、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になります。
他に必要な物としては被相続人の戸籍謄本や登録免許税の額を算出する指標とするためにその不動産の固定資産税評価証明書も必要になります。
素人ではなかなか手間がかかり面倒なので司法書士などに依頼するケースも多く、その場合は数万円程度の報酬が必要になるでしょう。
■手続き3:相続税の申告と納税
相続財産に不動産を含むか含まないかに関わらず、我が国の税制では相続財産は課税の対象になります。
日本の税金はお金や財産価値のあるものが人や法人の間で移動した時に課税するのが基本ですが、相続では故人から相続人などに財産が移転するので、ここに目を付けられた形です。
相続財産に対してかけられる税目を相続税といい、この手続きのことを考えなければなりません。
相続人など遺産を貰う立場の方が覚えておかなければならないのは、例えば5000万円の不動産を相続で承継したからと言って、単純にこれに相当する相続税を納めるわけではないということです。
相続税は不動産以外の現預金や有価証券など全ての財産を合算して考えなければならないのです。
そしてもう一つ大事な「基礎控除」の存在は絶対に知っておきましょう。
これは相続という人の死に対してかけられる税金に対する国民感情への配慮のため、一定の額の遺産までは相続税の課税を免除するために作られたものです。
近年この基礎控除の枠が減ってしまい、税負担が増える方が増加してしまいましたが、それでもかなり大きな控除枠の為多くの事例で相続税の負担を無くしたり、税金額を減らしたりする効果があります。
計算式としては、「基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
この額の遺産までであれば相続税がかからないので納税だけでなく申告も不要になります。
基礎控除は非常に有効で大切なので掘り下げて解説します。
遺産の価値は誰が判定するのかというと、基本的には税務署ではなく相続人等の権利者が自分で考えます。
問題になるのは素人が相続財産の評価をしなければならないということです。
相続税の額を算出するための「相続税評価額」というものを算定しなければならないのです。
現預金はそのままの価値ですが、不動産の価値はどのようにして判定するのでしょうか。
実はこれが素人には非常に厄介で、その不動産が土地か建物かによっても評価方法がわかれます。
土地の場合は市街地等にある物件の場合基本的には「路線価」という指標を用います。
土地は国によって一定の基礎評価を受けており、これを路線価という形で公表しています。
しかしこれは国が定める基本の指標であり、実際にはそこに様々な補正を加えて実際の不動産の価値を判定しなければなりません。
例えば当該物件が自宅の土地など自分で使用する自用地なのか、アパートなど他人に貸すための土地なのかによる利用形態による補正、その土地が所在するエリアが住宅地区なのか、商業地区や工場地区なのかなど区分による補正、道路に面するところからどのくらいの奥行きがあるのかによる奥行補正、角地や準角地などによる影響補正など様々な補正を施さなければならず、正直なところ素人ではかなり難しい作業になります。
路線価が無い郊外などの土地は「倍率方式」、宅地以外は宅地比準方式が適用になったりと複雑です。
家屋の評価は土地よりは複雑ではないものの、貸家などの場合は借家権割合の調整などが必要になります。
また政府が用意した特例や特別控除など、不動産の価値を計算上下げて、もって相続財産の額を減らし、相続税の負担を減らす措置が用意されています。
これは知っていなければ利用できませんが、上述したように非常に手間がかかるうえに複雑なため、相続税の申告や納税は税理士などの専門家に依頼すると安心で安全です。
税理士はその筋の専門家ですから、特例なども上手く活用して税負担を極力減らすようにしてくれるでしょう。
自分で行う場合はさらに基礎控除の枠に収まるように、非課税財産や債務控除などの概念をフルに活用して相続財産額を計算上減らす工夫が必要です。
非課税財産とは厳密に言えば故人の財産と言えるものでも、国民感情への配慮や政策上の取決めによって遺産の総額に算入しなくても良いものをいいます。
例えば墓地や仏具、あるいは香典など一定の葬儀関係の財産や、生命保険金の一部、退職手当金の一部、一定の寄付や公益事業用財産などがあります。
生命保険金と退職手当金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税財産とすることができます。
債務控除とは故人が持っていた一定の債務を相続財産から控除し、遺産額を減らすことができるものです。
例えば借入金や未払いの医療費、未払いの住民税や固定資産税など一定の税金、通夜の費用や葬儀費用、葬儀前後で通常必要とされる出費などです。
控除できないものもあり、墓地購入にかかる未払い金、弁護士費用や税理士費用、土地の測量費用や登記費用、香典の返戻費用、故人の死後の墓地購入費用などは控除できません。
さらに、逆に相続財産に算入しなければならない「みなし相続財産」というものもあります。
本来は故人の財産とは言えないものでも、実質的に故人の権利に帰属するとみなされるものです。
一定の生命保険金や生命保険契約に関する権利などがあります。
注意が必要なのが相続開始前3年間になされた相続人への財産の贈与を相続財産に組み戻す「3年以内の贈与財産の加算」です。相続税逃れのために生前に財産移転する行為に対する牽制の効果があるものです。
同加算とみなし相続財産は遺産の総額を増やす方向に働くものですが、税理士などの専門家を利用しない場合はこれらも相続人が自己の責任で計算しなければなりません。
こうした計算の結果、基礎控除内に収まれば相続税の申告納税は不要になります。
基礎控除を超えた場合はさらに相続人個人個人の事情を反映した複雑な計算をして最終的な相続税額を算出し、税務署に対して申告、納税を行います。
■手続き4:固定資産税の納付
不動産は実は所有しているだけで税金がかかるという厄介な側面も持っています。
今まで不動産を所有したことがないという方でも「固定資産税」という名前は聞いたことがある人が多いと思います。
固定資産とはつまり不動産のことを指しており、これが所有しているだけで課税される税目になります。
固定資産税は国税である相続税と違って市町村税となり、管轄もその不動産の所在を管轄する地元の市区町村です。
相続税と違って固定資産税は地元の役所が勝手に不動産の財産評価をし、必要税額を算出して納付書を送ってきますので、これに従って納付することになります。
固定資産税の算出の為に用いる指標は相続税とは異なり、独自の指標を用いて地元の役所が「固定資産税評価額」というものが設定されます。
相続税算出の為に用いられる「相続税評価額」よりも若干低めの価値評価になるのが普通です。
納税義務者はその年の1月1日時点で所有権を有する者になるので、相続で不動産を取得した場合は翌年から納税義務者となります。
相続コンテンツ一覧
- 生命保険を使った相続税対策
- 愛人、内縁の妻に財産を相続させたい!やっぱり本妻に財産を取られる?
- 相続についてのお尋ねが届いたら
- 遺言書のトラブルについて
- 相続人が未成年の場合はどうすればいいの?
- 相続時精算課税制度のメリットデメリット
- 相続の際にも使える!不動産売却の際に使える3,000万円控除
- 知っておきたい生前贈与の種類
- 〜知って得する!相続税の仕組み〜【養子にすると節税になる?】
- 遺産分割調停の仕組みと実際について
- 受取人を変えるだけで節税に?!「相続税と生命保険の関係について」
- お墓、仏壇を購入すると節税になる?!
- 知っておきたい新制度 ”法定相続証明情報制度” とは?
- 相続財産の整理ってどうすればいいの?
- これだけは知っておきたい!!相続がおこった時のマメ知識
- 遺言書の活用~メリット・デメリット~
- 隠れたリスクがいっぱい。相続した不動産を空き家にしておく危険性
- 『気付いた時にはもう遅い?相続の準備でやっておくべき事』
- 【音信不通】連絡を取ったことがない相続人がいる場合
- 【遺産の放棄はできる?】相続放棄についてまとめました。
- 【遺産相続】相続財産評価、現預金以外の評価について
- 相続税の申告と納付について
- 相続関連手続きスケジュール
- 相続人と相続分の関係
- 今からできる相続対策!生前贈与の活用法
- 子なし家庭が注意すべき相続の注意点6点
- 子供が結婚、家の面倒見てやるか・・親から子への住宅取得等資金贈与のポイント5つ
- 不動産を相続した時にするべき4つの手続き
- お得な生前贈与をフル活用して節税する
- 相続税申告の税理士報酬はいくらくらいかかる?【相場】
提携して一緒にプロとして相続対策をしてくださる司法書士の方へ
まずはご連絡くださいませ。
その後、詳しいお打ち合わせをさせてもらえたら幸いです。
相続のプロ税理士を探されている方もご連絡ください。

【予約制】平日 11:00-18:00 / 時間外・土日対応可能