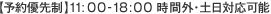相続時の手続き
相続人が未成年の場合はどうすればいいの?
相続が発生し、遺産を分割するためには相続の手続き(法律行為)が必要になります。
しかし、相続人は、必ずしも成人とは限りません。時には未成年などの「制限行為能力者」が法定相続人となりうる場合があります。
このようなケースにおいて「どのように手続きを行ってゆくのか」について、仕組みの理解を深めながら順番に説明をしてきいきたいと思います。
そもそも未成年って何歳まで?
民法では「20歳に達した時を持って成人(行為能力者)とする」というルールが設けられております。
つまり20歳以下であれば「未成年」ということになりますので、単独で法律行為を行う場合は原則として親権者の同意が必要です。
未成年者が単独で行った行為は取り消すことができます。ただし例外として、男性は18歳、女性は16歳において婚姻をした者については、20歳以下でも成人(行為能力者)としてみなされます。※お酒や喫煙に関する年齢規制についてはこの適用を受けず、年齢的な未成年者という扱いになります。
制限行為能力者
法律上では法律行為を行うことができる方のことを「行為能力者」と言います。
未成年はまだ成人ではないため、行為能力については十分な判断ができないということから「制限行為能力者」として親権者の同意が必要と定めております。
難しい言葉かもしれませんが、この言葉は未成年に関わらず相続の際は特に重要な言葉になりますので、知っておくと良いでしょう。
相続手続きにおける制限行為能力者の関係
相続の発生により、法定相続人となる方は相続の手続きをしなければなりません。
しかし、制限行為能力者が存在する場合は勝手に進めることができなくなります。
なぜなら制限行為能力者の権利について行為能力者が代理をして意思の表示をしなければならないからです。
例えば、未成年の相続人を相手に法定相続分の話をしても何のことやら難しすぎるため、理解して正しい判断をしてもらうことは難しいはずです。
行為能力を有すると判断されている方(少なくとも行為能力者である成人)の判断が必要になります。
何で代理人が必要なの?
1、判断能力の差が発生してしまうため、法律行為自体にリスクをもたらす
制限行為能力者である未成年が親の同意を得ずに法律行為を行うことができたとすれば、いろいろな問題が起きると言えるでしょう。
例えば、未成年でも不動産の売買契約あるいは各種契約を単独で行うことができる、担保があれば銀行でお金を借りることができる、など成人と同じ範囲の法律行為までもが可能になる反面では、危険にさらされるリスクもあります。
成人に比べて知識や経済力の差があるにも関わらず、騙されて契約をさせられてしまったり、逆を言えば未成年が成人を相手に虚偽の説明をして不当に利益を得られるとすれば、双方の財産を侵害しかねません。
制限行為能力者が法律行為を単独で行うことができないのには理由があり、このようなことが起きないよう保護することを目的として設けられているルールなのです。
2、必ずしも制限行為能力者は未成年ばかりではない
相続人が成人でも「制限行為能力者」である場合には、代理人を立てる必要があります。
例えば、障害を持っており正しい判断ができなかったり、意思表示ができない場合などは本人を保護するものがなくなってしまいます。
無理やり同意をさせられてしまっても、自分の意思を主張することが難しいなど、一方的に不利になってしまったのでは権利を侵害されてしまいます。
認知症などもその一例です。そのため、判断能力が不十分であると判断された場合には「特別代理人」を立てなければ、相続手続きを行うことができません。
ここにルールがないとすれば、いてが認知症や判断能力を欠くという事実を武器に悪いことを働いてしまう人が現れてしまいます。
制限行為能力者の代理人
代理人の必要性について、お分かりいただいたところで遺産分割における未成年(制限行為能力者)の代理人について考えてみましょう。
未成年の代理人は親権者である両親ですが、相続の場合はこればかりではありません。
例えば、自分の両親のうちどちらかの相続が発生してしまった場合、相続人は残された配偶者と子供であり、子供の代理人が親である配偶者だった場合に、子供が不利になってしまうという可能性があります。
相続手続きにおける未成年者の特別代理人
未成年者の代理人としての親権者が利益相反の場合については、裁判所に申し出ることで第3者を特別代理人に選任することができます。
そして裁判所が定めた特別代理人は、親権者に代わり未成年者の代理人になることが許されます。また裁判所に特別代理人選任の手続きを行う場合は親権者が行う必要があります。
代理人は指定できる?
特別代理人を限定するルールはありませんので、選任は自由です。
遺産分割などの相続財産の取得に関する代理人については、直接利益を得る関係の対象以外であれば誰でも構いませんが、その方に「万が一」の事があった場合までは補償がありませんので、司法書士などの専門家に依頼をするという方法もあります。
また、類似ケースとして制限行為能力者に関しては、後見人や成年後見人という代理人の方法もあるため、専門家に相談をすることで不正のない誠実な手続きが行えるというメリットもあります。
特別代理人の選任の流れ
1、裁判所へ特別代理人選任申立て
特別代理人選任の必要性を問う対象の方の住所地の管轄の裁判所に対して特別代理人の選任の申立てを行います。
管轄の裁判所並び申し立ての様式は裁判所のホームページより確認ができます。
2、必要書類
未成年者・親権者の戸籍謄本、特別代理人選任候補者の住民票または戸籍の附票、利益相反に関する資料(遺産分割協議書)などが必要になります。※必要書類は省略しておりますが、このほかにも代用可能な書類もあります。また、入手不可能な書類については申立書提出後に追加資料として提出をすることもでき、場合によっては追加提出を要求されるものもあります。
基本的にはこれだけであり、裁判所への申し立てというのが流れになります。
遺産分割協議における未成年者にあっては特別代理人(親権者以外)を選任する必要があり、そのためには事前に裁判所へ「特別代理人選任の申立て」を行う必要があります。
遺産分割協議については利益相反に関する資料として、あらかじめ作成した遺産分割協議書を提出し、その内容について添付された未成年者本人並びに親権者に変わる特別代理人に対しての特別代理人の権限が認められることになります。
分割協議書の内容が明らかに不公平である場合や、明らかに法定相続分を下回る場合などについては例外として特別代理人の選任が認可されない場合があります。
まとめ
単なる手続きというよりは、未成年者や制限行為能力者に不公平や不平等が生じないよう、保護することを目的としている背景があることがお分かりいただけましたでしょうか?ついつい「難しい」手続きと考えてしまいがちですが、こうした手続きがあるからこそ保護されていると言えます。法律は面倒な手続きを設ける厄介者ではなく、本来得られるべき財産を保護するためのアイテムなのです。
相続時精算課税制度のメリットデメリット
相続を行うにあたって気がかりなものの一つが相続税になります。生前贈与しておけば相続税を下げられると思っている方もいるでしょうが、骨格としては相続税逃れが横行しないよう、生前贈与による贈与税のほうが不利になるような制度になっています。
一方で特例的には生前贈与を促す狙いのものもあり、その一つが相続時精算課税制度となります。
相続時精算課税制度の概要
|生前贈与を促す制度
制度の趣旨をごく簡単に言うと、相続すべき財産に対して、生前贈与を促すものです。この制度を使って生前贈与した財産は、相続税の申告の際に相続財産と同等の扱いがされます。
|2,500万円の贈与税非課税枠と計算例
通常は、年間110万円を超える贈与をすると、超えた分に対して贈与税がかかります。相続時精算課税制度を活用することにより、2,500万円までの贈与について非課税となります。
これは年間でなく、特定の贈与者から生涯を通じての枠となります。例えば父親・母親・子がいる世帯で、父親からの贈与財産には相続時精算課税を適用するとします。そして3年にわたり、父母両方から下記のような金額で贈与が行われるとします。
| 父親から | 母親から | |
| 1年目 | 1,000万円 | 150万円 |
| 2年目 | 1,000万円 | 100万円 |
| 3年目 | 1,000万円 | 150万円 |
贈与税の計算は、下記の通りになります。
1年目:(150万円-110万円)×10% = 40万円
2年目:0円
3年目:(3,000万円-2,500万円)×20% + (150万円-110万円)×10% = 100万円 + 40万円 = 140万円
相続時精算課税制度の特定贈与者にあたる父親からの贈与財産に関しては、2,500万円を超える3年目から20%の税率で課税されます。2年目までは、2,500万円の枠内に収まるので課税されません。
相続時精算課税制度の特定贈与者にあたらない母親からの贈与財産に関しては、110万円を控除して贈与税を計算します。2年目は110万円を下回っているので課税されませんが、1年目は税率10%で課税され(控除後の財産価額に応じて税率は変わります)、3年目は父親の分と合算して贈与税を支払います。
|制度適用の手続き
手続きを適用する場合の最初の贈与税申告(申告期間は贈与した年の翌年2月1日~3月15日)で届出を税務署に出すことになります。上記の事例では、特定贈与者として父親の氏名を記入します。
また特定贈与者の要件として、(贈与を行う年の元日時点で)60歳以上の父母・祖父母という要件があります。本人には20歳以上という要件があります。
また相続時精算課税の特定贈与者から贈与財産があった場合は、非課税の枠内にあっても必ず申告することになります。例えば上記の計算例では、2年目の贈与税は0円ですが贈与税申告書は提出してください。
|相続税申告を行う際には
相続時精算課税というくらいですから、特定贈与者が亡くなり相続税申告を行う場合には、制度を適用して申告した贈与財産を考慮することになります。
例えば上記の計算例に関して、その後父親からは何の贈与も受けずに父親が死亡し、相続財産の総額が5,000万円、債務額は800万円であったとします。そして法定相続分どおり、母親と子が1/2ずつ相続したとします。
相続時精算課税制度を利用していなければ、この場合の相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×2=4,200万円ですので、課税遺産総額は5,000万円-800万円-4,200万円=0円となり、相続税はかかりません。
しかし3,000万円の贈与財産に関して、相続時精算課税を適用していますので、課税遺産総額は3,000万円なのです。
母親の課税価格は(5,000万円-800万円)÷2=2,100万円、子はここに3,000万円をプラスして5,100万円となりますので、比率は母親が0.29、子は0.71となります。
母親の相続税額は、3,000万円×0.29×10% =87万円 になります。
子の相続税額は、3,000万円×0.71×15% -50万円-100万円=169万5,000円 になります。
子に関しては、3年目の贈与の際に(父親からの贈与財産に係る)贈与税100万円分を控除しています。
複雑な計算ですが、贈与財産を相続財産に足して、20%の税率で払った贈与税額を差し引くという意味で「相続時精算課税」なのです。
相続時精算課税制度のメリット
|2,500万円まで一括贈与しても贈与税がかからない
上記の計算例は、3年にわたって贈与している例ですが、1年間で2,500万円の贈与を行ったとしても贈与税がかかりません。相続時精算課税を適用しない通常の暦年課税の場合は、(2,500万円-110万円)× 45% - 265万円= 810万5,000円と高額の贈与税がかかります。
1年でも何年かかけての贈与でも活用できますが、一括で贈与した場合のほうが通常の暦年課税と大きな差が生まれます。
|評価額が贈与時<相続時の場合は有利に
相続時精算課税制度を利用した際に相続財産に加算する贈与財産は、贈与時の価額です。贈与財産が不動産や上場株式である場合、相続時と贈与時は同じ額であるとは限りません。
近年のようにこうした財産が順調に値上がりしていく場合は、値上がりする前に生前贈与したほうが税金面でも有利になります。
相続時精算課税制度のデメリット
|土地贈与の場合、小規模宅地の特例が使えない
相続時精算課税を利用するにあたって、一番気をつけないといけないのがこの点です。
小規模宅地の特例とは、土地の相続税評価額を最大8割引き下げるための特例です。この特例を受けるためには、相続人に条件があります。
被相続人と同居している場合は、被相続人が死亡してその住み家を相続し、相続税の申告期限までずっと住み続けていることが条件です。
同居していない場合は、相続開始前3年以内に持家が無く(賃貸物件で暮らしている)、被相続人の住み家を相続して相続税の申告期限までずっと所有し続けていることが条件です。同居している場合と違って相続した不動産に住むことまでは要件となっていませんが、被相続人に配偶者がいたり、同居している法定相続人が他にいたりすると対象外になります。
例えば相続時精算課税の概要の事例で、父名義の持家があり、子は別居して賃貸物件で暮らしている場合を考えます。父が先に亡くなり子が父名義の持家を相続したとしても、母がまだ存命であればこの特例は活用できません。
また母が先に亡くなってから父が亡くなり、子が持家を相続した場合は、この特例が活用できます。ただ子には弟がいて、弟が実家に暮らしているようなケースはこの特例は活用できません。
どれだけ評価額が下がるかですが、上記の要件を満たす場合の相続土地は特定居住用宅地等といい、どのような広さであっても特例は活用できます。ただし330㎡までの部分について8割の評価減となっています。
もし父から相続した土地が330㎡以内で、原則的な相続税評価額が4,000万円であった場合、小規模宅地等の特例を活用すると800万円にまで下がります。
なお不動産が居住用でなく事務所として使っていたり、アパートのような貸付物件になっていたりする場合は、要件や評価額の下がり方は異なります。
もし相続を考えた場合に小規模宅地等の特例を活用できる余地があれば、不動産については相続時精算課税を使った贈与はしないほうがいいケースは多いと言えます。
|課税を相続時に繰り延べる制度であり、かつ物納の対象外
概要部分で相続税申告まで触れていますが、そこまで見据えてこの制度を活用することが重要です。贈与時には贈与税を支払わなくて良いかもしれませんが、その後相続となった場合に相続税を払うこともありうるからです。
相続税がかからないほどの財産しかない場合は、贈与税の節税になる場合もなります。ただどのケースでも節税になってお得だと決めつけず、あくまでも課税を先送りしていると考えてください。
また相続税がかかってくるケースで手元の資金で支払えない場合、一定の要件を満たした場合に物納が認められます。相続した物件などをもって、相続税の現金支払いに替えるというものです。
相続時精算課税対象の贈与財産は、相続税申告における相続財産に加算されますが、物納対象の財産としては認められていません。
|不動産取得税・登録免許税の税率が高い
これも小規模宅地等の特例と同様不動産の話になりますが、相続・贈与いずれにしても名義変更になるため、相続税・贈与税以外にも不動産取得税・登録免許税がかかってきます。
これらの税金は、相続と贈与では税率が異なります。まず不動産取得税は、相続においてはかかりませんが、贈与では課税されます。
登録免許税の税率も、相続では0.4%なのに対し、贈与では2.0%と相続時精算課税を活用したほうが損することになります。
遺産分割調停の仕組みと実際について
人間の死亡によって発生する「相続」において、亡くなられた方の血縁関係者などの相続人が財産を相続する際に、「誰」が「何」を「どれくらい」取得するか相続人間で話し合いをすることで決定します。
これを「遺産分割協議」と言います。
財産については、当然不公平が生じないよう均等に分配すべきというのが一般的な考え方であり、公平に取得したいものです。
しかし、財産の取得については遺産分割協議によって決議される事ばかりではなく、人間の感情が入ってしまう場合があります。
そうなると話が前に進まずトラブルに発展してしまい、相続の手続き自体が止まってしまい、財産の取得を認められたことになりません。
このような場合に行われるのが「遺産分割調停」です。相続人だけでの遺産分割協議ではなく管轄の裁判所が間に入り、公平に客観視できる立場を設けることで、最も適切と判断される遺産分割へと誘導します。
遺産分割にルールはないの?
遺産分割協議において、被相続人の相続に関係する法定相続人に対しては「法定相続分」というルールが登場します。
これは民法で定められている法定の相続分になりますので、このルールに従った相続分については、最低限の保護をされることになります。
Aさんは財産をもらうが、Bさんは財産をもらうことができないということが発生しないように、決められたルールに沿って法定相続分が認められているのです。
どうして最初からルールで決めないの?
相続財産は亡くなられた方の想いや相続先の希望など、死後も財産についての所有権を尊重すべきという目的のもと保護されております。
人間が死を迎えた時、全ての相続財産が法律によって規制されコントロールされてしまったのでは、亡くなられた方の財産に対する所有権や自由を損害してしまうことになるため、あくまで相続人の話し合いが優先されています。
相続人間での遺産分割協議は民法に優先して認められる権利であり、本来持つべき財産権の尊重を第一に決議が完了しない場合には「法定相続分」に従って相続財産を取得する権利を主張できるという仕組みになっております。
遺産分割調停へ発展するケース 〜トラブル編〜
できれば避けたいところではありますが、相続は時に「争族」と表現されることもあり、金銭価値をもつ財産の発生には人間の感情や欲が働いてしまうケースがあります。
あるいは長い人生の中での疎遠となってしまった事実血縁関係者と遺産分割協議をする場合もあり、実際には会ったこともない方が相続人として登場せざるを得ない場合にトラブルへと発展するケースがあります。
その1争族の相続財産
いざ財産となると、人間の死とは無縁の感情が働いてしまうケースは少なくありません。遠方に住んでいる場合や、各種段取りや管理には関与していない場合などにおいても、相続財産はきっちり平等に分けるべきであるという意見が出た場合、不公平をきっかけにトラブルへと展開してしまうことがあります。
こうなると、話し合いでは解決できず「法定相続」というルールに従って相続を行うしか無くなってしまいます。「相続をきっかけに人が変わってしまった」あるいは「相続がきっかけで疎遠となってしまう」ということは、意外にも多いのが実際です。
その2会ったことのない相続人
自分は会ったこともない人間が「相続人」として登場するケースがあります。
「会ったことも話したこともないのに遺産分割協議には関係ない!」と割り切って話を進めたいところですが、法律は許してくれません。
亡くなられた方に先妻夫がいた場合で、その先妻夫との間に子供がいた場合は、その子供は「法定相続人」として認められます。
相続財産の遺産分割においては相続人として財産を取得する権利を有しているため、実質無関係となってしまった存在であっても「法定相続分」は認められます。
遺産分割調停の実際
遺産分割協議がまとまらないケースは様々であり、悲報にも親族同士で金銭トラブルなどから争いが発生することもありますが、相続財産については相続手続きを行わなければなりません。
こうした場合には遺産分割調停を避けられなくなります。まずは遺産分割調停についてポイントを整理しておきましょう。
まずは、調停によって何をどう決めるのかを知っておくことが必要になります。
これらの手続には相続の知識が必要になりますので、代理人として認められている「弁護士」などに相談する事例が多いです。
またはそのほかの専門家「司法書士」「税理士」などもそれぞれの役割分担がありますので、どの専門家がどのように役割を持つのかをよく理解した上で、事前に相談をするといいでしょう。
1、調停の手続きについて
まず初めに管轄裁判所に対して必要書類の提出が必要になるため、ここに不備があってはいけません。
必要書類を集めることが先決になります。ここで重要なことは、各種専門家への相談は可能ですが、実際に裁判が絡む場合には代理を許されているのは「弁護士」のみとなります。
2、必要書類の収集
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本並びに法定相続人の現在戸籍一式による相続人関係証明情報が重要になります。
一つでも欠陥があると手続きは開始できず、不足分を請求する必要があります。これらは専門家に依頼することで職権を利用して収集してもらうことも可能です。
3、財産の特定
亡くなられた方の財産についての証明情報になります。
わかりきっているようで実は厄介なのがこの証明情報です。
ここでは「確か・・・多分・・・おそらく・・・」では財産を特定したと判断されません。
土地建物などの不動産については不動産登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などから特定や算出ができます。
金融機関などについては、残された情報が頼りですので通帳やキャッシュカードがある場合は該当の金融機関へ、亡くなられた日付時点の残高証明発行を行うことで証明できます。(証券や株なども同じ要領で照会をかけます。)
財産を公式に証明できる情報の確保をしましょう。保険金などについては「満期金」などがある場合は注意が必要です。
受取人指定の保険金については、遺産分割には関与せず相続税のみの対象となります。
4、遺産分割調停の申し立て
情報が揃えば、あとは管轄の裁判所へ遺産分割調停申立書を提出します。
管轄の裁判所については亡くなられた方の最後の住所を管轄する裁判所になり、裁判所のホームページや直接聞くことも可能です。
5、裁判所へ出頭
調停の期日が確定したら、裁判所より相続人へ通知が届き1回目の話し合いが開始されます。
出頭した相続人及び裁判所の選任した調停委員を交えて協議が開始されます。ここで話が完結しない場合は後日再び出頭することもあります。
ポイント
1、遺言書がある場合は、遺言内容が優先となる場合がありますのであらかじめ存在の確認をしておきましょう。自筆証書と公正証書とでは手続きや必要書類も異なりますので注意が必要です。
2、司法書士は小額訴訟において簡易裁判の代理人を許されておりますが、家庭裁判所の家事審判の代理権はありません。ただし裁判所提出書類の作成を代行することができますので、事前情報収集や相続人特定なども踏まえて依頼を行うことが可能です。
3、税理士もまた「相続税」という分野に関係してくるため、財産が多い場合は後の相続税申告を踏まえて、事前に相談することも視野に考えておくと良いでしょう。
知っておきたい新制度 ”法定相続証明情報制度” とは?
・新しい制度の誕生
従来と新制度導入の違いについて
平成29年5月29日(月)から全国の法務局において制度が始まることが確定し、制度導入に伴う今後期待される相続の手続きの簡略化についてご紹介します。
法務局は「登記」を行う機関であり、公式に不動産の所有権を有する旨を証明するために行う手続きの中に「相続」という登記があります。
この相続の手続きに際して、今後の新制度導入による簡略化が期待されております。
・相続の登記
不動産所有者が死亡した場合に、法定相続人によって「相続による所有権移転の名義変更手続」を行う必要があります。
不動産の所有権に関しては所有者が生きている間に主張することができ、死亡を持って失効してしまいます。
そのため、後継者として相続人はその不動産を受け継ぐ必要が出て来ます。名義人が不存在では、土地の管理はもちろん売却することも手続きも行うことができないからです。
そのためには「相続の登記」の作業が必要になります。相続登記を行うことで、亡くなられた方の不動産について誰が次期所有者であるかを明確にします。
・相続登記の流れ
相続が発生すると、不動産の所有者の「相続人」であることの証明情報や、相続に関する遺産分割協議書などの「必要書類」を添付して申請をすることになります。
ここで「相続関係を証明する情報」について説明をしておくと、被相続人(亡くなられた方:対象不動産所有者)の出生から死亡までの「戸籍謄本」一式、亡くなったことを証明する「除籍謄本」、最後の住所を証明する「住民除票」または「除付票」を基本情報とし、相続の関係を記す「相関図(家系列を表にまとめたもの)」に加え、それぞれの相続人の現在の「戸籍謄本」(転籍している場合は、その過程についての除籍も全て)が必要になります。
他にも登記申請書などがありますが、専門職の方や手続きに慣れている方でなければ書類回収も思うように前に進みません。多くの場合は「司法書士」などの専門家に依頼するケースが多いです。
・法定相続証明情報制度について
法定相続証明情報制度は、相続登記に必要な「相続関係証明情報」を確認した上で、「法定相続証明情報」として公印付きの証明書類を発行してくれるという制度になります。
通常の相続手続きに必要な書類といえば、その環境にもよりますが膨大な量の書類を準備することになります。
しかし、法務局が発行する「法定相続証明情報」であれば、戸籍謄本を一括した内容を証明してくれるため、手続きの際の戸籍情報を全て添付しなくても良いということになります。
添付する情報量が簡略化されるため、手続きの都度集めなければいけない書類もこの「法定相続証明情報」によって法務局公認の公式書類として認められることになります。
・法定相続証明情報制度のメリット
1、手続きの都度に大量の戸籍情報を提出する必要がなくなり、書類の簡略化ができる。
2、各種手続きにおいて、相続関係証明書類として使用することができる
3、相続登記にも使用することができる。
4、手続きの量に合わせて発行することで、手続きを同時進行することができる。
亡くなられた方の相続手続きは「不動産相続登記」のみならず、様々な財産に応じてそれぞれの手続きを行わなければなりません。
例えば、亡くなられた方が「銀行口座」を持っていた場合など、名義人が指定されているものについては「財産」として扱われるため相続の手続きが必要になります。
この際、相続人全員の意思表示(金融機関所定の解約用紙、代表人がいる場合はその内容を記す遺産分割協議書)に合わせて、「戸籍」が必要になります。
財産の管理というのは非常に繊細な問題であり、相続人の情報に欠陥が無きよう念入りに確認が必要になります。
そのため、多くの金融機関は書類を預けた後に相続担当部門において確認作業など、とにかく時間がかかってしまいます。
法務局や金融機関であっても、相続関係を証明する情報は「戸籍」という公式書類しか認められないため、いづれにしても手続きの都度人間が確認をすることになってしまいます。
これらの戸籍情報については「個人情報」であることから、原則本人しか請求ができない情報のため、勝手に行政機関などが相続関係を調べるということはできない故に、このようなことが起きてしまいます。
各種相続手続において一番頭を抱えるのが「戸籍情報の確認」と言っても過言ではありません。状況次第では相続関係図も膨大な規模のケースもあり、その情報量は驚くほどの枚数に至る場合も珍しくありません。
・制度活用の期待例
期待される活用方法については、上記「相続登記の流れ」において記載した「必要書類」について大きく影響してくることが期待されております。
各種相続手続においては、法務局が発行する「法定相続証明情報」のみで相続関係を証明することができ、戸籍情報を提出する手間が省ける期待がされております。
また、何と言っても法務局が確認済みという「信頼性」が非常に高いことで、相続関係情報についての保証がされていることです。多くの手続きでは、この「相続関係情報」に欠陥が発生するため、手続きが止まってしまうケースが多いのです。
そのため、個人が持参する資料の信頼性については、再度確認という定義が発生してしまいます。法定相続証明情報の提示によって、相続手続きは大きく簡略化されることが見込まれます。
制度活用のさらなる期待については、自分で相続手続きがしやすくなることです。
相続の場合、「司法書士」が法務局へ提出する書類の代行作成業務を行えることから、不動産の相続登記の大半は依頼するというケースが多いです。
もちろん自分で行うこともできますが、欠陥なく十分な必要書類を全て自分で作成するのは、経験者でない限り非常に困難であると言われております。
そこで司法書士に依頼をすることで相続登記の手続きの一環に、この「法定相続証明情報」をもらうことで、そのほかの財産整理については「戸籍情報」ではなく「法定相続証明情報」で手続きが行えるということになります。
相続手続きは専門家でなければできないという概念を変え、自分でも手続きを行うことができるよう証明情報を法務局が発行してくれるというのがこの制度の趣旨となっているのです。
また、同時進行の手続きの可能性についても期待されております。金融機関が3社あった場合には、1社終わるごとに処理が返却され、次の金融機関へ書類を持っていくという手間がかかってしまいます。
時間短縮のために戸籍を3通ずつ請求するとなると、とにかくお金がかかってしまいます。
しかし、「法定相続証明情報」を必要通数発行することで相続証明情報としての役割を持つため、同時に手続きを進行させることが期待されています。
・これからの相続手続き
時代とともに、手続きはデジタル化されてきております。
そんなデジタル化が進む時代の中でも、人が亡くなった場合の手続きなどは未だに書類を通じての申請が主流であることから、難しい手続きとばかり認識されてしまいがちです。
だんだんと制度の普及により、一般の方でも手続きができるよう国が動き始めていることは事実であり、相続登記についても自分で行えるよう法務局がシステムの開発に努めているのが実際です。
『気付いた時にはもう遅い?相続の準備でやっておくべき事』
「終活」や「エンディングノート」と言う言葉も今では当たり前のように耳にしますが、そんな言葉ができたのはごくごく最近の事です。
少し前までは公証役場で作成してもらう「遺言状」が主であり、亡くなった後に「おばあちゃんは大きなダイヤを持ってたはず!」なんて家族総出で探し回るなんて言うちょっとした笑い話もありました。
いつかはやっておかなきゃ。と思いつつも、つい先延ばしにしがちな相続の準備。
相続は大きな金額のお金が絡む事が多々あり慌てて手続きをしてしまったばかりに損をしてしまうのもよくある話です。
ご自身や家族の死について考えるのはとても悲しい事のように感じてしまいますが、相続について事前に準備をする事は残された家族の幸せの為にとても大切な事です。
もちろんいつまでもお元気なのが一番ですが何があるかわからない人生、残されたご家族がスムーズに手続きをできるよう普段から相続の準備をしておきましょう。
●定期的に資産のたな卸しを
相続をする際に財産として評価される物は様々です。
今住んでいる自宅の土地や建物・預貯金はもちろんですが、株や公社債、貴金属や絵画なども相続財産として評価されますしバブルの頃に流行ったゴルフ会員権も相続財産としてみなされます。
不動産や貴金属・絵画など目に見える物であればおおよその見当が付くので比較的わかり易いでしょう。
ですが、預貯金や株は通帳などで履歴が見れなくては本人以外には把握する事ができません。
同居している家族であればまだ良いですが何年、何十年も前に独立し別々に住んでいた家族の事は思ってる以上に知らないものです。
こう言った、普段は家族でも目にする事の無い資産に関しては年に一度で良いのでご自身でたな卸しをし、一覧にまとめておきましょう。
ご自身で把握する為のいい機会にもなりますし、何より残されたご家族が混乱するのを防いでくれます。
●重要書類の保管場所は信頼できる人に伝えておく
先に書いた資産の一覧もそうですが不動産の登記識別情報(昔で言う権利証の事です)や預金通帳・実印など重要な書類はまとめておき保管場所を信頼できる身内に伝えておきましょう。
自宅に置いておくのが心配であれば銀行の貸金庫を利用するのもお勧めです。
貸金庫は事前に届出をしておけば本人以外でも入出庫が可能です。
大切なのはどこに保管しているか、ご自身以外の誰かが把握している事です。
相続には不動産の売買が付随する事が多々ありますが不動産を売却する時には登記識別情報(権利証)が必要です。
1つの例として不動産を挙げましたが、不動産に限らず預貯金や株など資産と言われる物を相続する際はそれに関する重要書類の提出を確実に求められます。
「貯金をしているとは聞いてたけど、どこの銀行だかわからない」
「株や投資信託の話はよくしてたけど、実際どれくらい持ってたのかさっぱり・・・」
と言った状況で、ゼロから調べていくのはとっても大変です。
それでも全ての資産が見つかれば良いのですがどこで資産運用をしていたのか結局わからず仕舞になってしまったりはたまた弁護士に依頼した事で余計な費用がかかってしまったり再発行をする為に時間とお金を要してしまったり。
書類の所在がわからない事は残されたご家族にとって想像以上の労力を生みますのでいざとなったら誰も把握してない!と言う事が無いように注意しましょう。
●万が一の時、連絡する人のリストを作成しておく
これはエンディングノートなどでよく言われる事ですがもしもの事があった時、連絡するべき人の連絡先をまとめておきましょう。
親戚やお友達はもちろん、仕事で繋がりの強い方やご近所付き合いのあった方、今までの人生を振り返れば連絡してほしい人の顔が次々と思い浮かぶのではないでしょうか。
人が亡くなった時と言うのは寂しい気持ちが溢れる反面、お葬式やら何やらで非常に慌しく1つ1つの事をノンビリやっている時間など無いものです。
そんな中で故人のお付合いのあった方や生前お世話になった方に連絡を取るのは負担の大きい作業の1つですがお付合いのあった方がわからない、ましてや連絡先がわからない、となるともはやお手上げになってしまいます。
そうならない様、万が一の時は必ず連絡してほしい「人生のアドレス帳」を作っておきましょう。
そして大切なのは預貯金を管理しているメインバンクや証券会社の担当者などご自身の資産を管理してくれている機関を必ずリストに載せておく事です。
生命保険をかけている場合は、保険会社の担当者も漏らさず記載しておきましょう。
そうすれば、もし突然の不幸が襲ってしまったとしてもご家族が慌ててテンヤワンヤになる必要がありません。
●やっぱり重要な効力を持つ「公正証書遺言」
いくらご自身が万全の備えをしていても身内同士での骨肉の争いと言うのはどうしても無くならないものです。
それまであまり見る機会が無かったようなまとまったお金を目にすると仲が良かった親子や兄弟、親戚同士で見るに耐えない争いが始まる事も珍しくありません。立場が違えば主張も違う、何とも悲しい事です。
そんな事態を避ける為に重要な効力を持つのがやはり「公正証書」による遺言状です。
公正証書は公証役場へ行き作成してもらうものですが公証人の印が押印されており、法的な効力を持ちます。作成費用は公正証書に記載する金額により異なりますが基本的には数万円~で作成が可能です。(もちろん相続カフェに相談いただければ税金面も考慮した遺言の内容についてアドバイスさせていただきます。)
「死人に口無し」とはよく言ったものでご本人がどんな相続を望んでいようと、それを生きてるうちに書き残しておかなければ亡くなってからでは意思を伝える事ができません。
そう言った意味で公正証書は、何にも劣らない正確な意思表示ができるのです。
余計な争い事を防ぎ残されたご家族がこれからも仲良く暮らしていく為にご自身の意思を公正証書に残しておきましょう。
まだまだ元気なうちは死に向き合う事やましてやその後に発生する相続の事などあまり考えないかもしれません。
ですが、それは人間誰しも必ずいつかはやって来る事です。
早いうちから万全な準備をするに越したことはありません。
まして相続は、身内同士の争い事として群を抜いて多いのが現状です。
家族の為を思って残した資産が、家族の中を引き裂く事になってしまったら本末転倒。
人生を終えた後に「さすがだね!」とご家族に思ってもらえる様な相続の準備を今から始めておきましょう。
【音信不通】連絡を取ったことがない相続人がいる場合
相続事案では普段付き合いのない人とやり取りが必要になることもあるので非常に気を遣います。
遠縁の親戚や連絡方法が分からない人が利害関係者になることも往々にしてあるので気苦労が絶えません。
例えば遺産分割協議書を作成して遺産を分割しようという場合、権利者全員の合意を形成する必要があるので全ての権利者が署名押印をしなければなりません。
もしその場にいないから、連絡が取れないからといって一人でも欠けた協議書を作成したところで、その協議書は無効となってしまうのです。
そのため相続事案では被相続人の血縁関係者を調べる必要があり、その結果連絡を取ったことのない者と意思の疎通を行わなければならないことも出てきます。
今回は連絡を取ったことがない相続人がいる場合にどうすれば良いかを考えてみましょう。
■相手と接触できる場合は
連絡を取ったことがない相手と相続事案について話し合うのは少し緊張しますが、遺言書に連絡先が書いてあるなど連絡先が分かる場合は丁寧な手紙を書いて相手方に相続が発生した旨を伝えましょう。
電話番号が分かっているなら電話で連絡するのもありですが、おそらく電話をかける方も緊張してしまうのと、電話を受けた相手方もいきなり相続の話をされたのでは面喰って落ち着いた対応ができないからです。
まずは手紙で相続が起きた旨を伝え、遺産の分割について話し合いたいのですがお時間を頂戴したいということを伝えてみましょう。
手紙には連絡先として自方の電話番号を記載しても良いですし、加えてメールアドレスを記載しても良いでしょう。
手紙であれ電話であれメールであれ、相手から接触があれば話し合いの日時や場所などを詰めます。
相続では遺産を貰うことができるということで好意的に対応してくれる場合もありますが、権利関係が絡むため緊張してしまったり、不必要に警戒されてしまうこともあります。
相手との距離を徐々に縮めるようなスタンスで丁寧な接触を心がけるようにしましょう。
■相手の連絡先が分からない場合
相続人調査では被相続人の戸籍を辿って生存している子や親兄弟など相続人となり得る者が他いないかどうかを確認する作業が入ります。
戸籍調査の過程で権利者となり得る者がいた場合、その者の戸籍の附表を取り寄せましょう。
戸籍の附表にはその者の住所地の異動についての情報が記載されるので、連絡先を調べることができます。
相手の住所地が分かったら手紙を出して相続が起きたことを伝えますがこの時もやはり文言には気を遣います。
相手からするといきなりの話ですから心理的に拒否感を持たれることもあります。
最近は詐欺事件なども横行していますから下手をすると「新手の詐欺か」などと警戒されて連絡を拒まれるかもしれません。
正体が分からない相手から「遺産分割について話し合いたい」と来られると警戒してしまうのも仕方がないかもしれませんね。
もし可能であれば相続関係図などを手紙に同封すると、相手も自分の地位を目で確認することができるので事態を把握しやすくなります。
最初の接触の段階でいきなり遺産分割協議書への署名押印を求めるなどしてしまうと一気に嫌悪感を持たれてしまい、以後のやり取りに非協力的になってしまうことが予想されるので控えて下さい。
■連絡が取れない場合はどうする?
相手の連絡先が分からずどうしても接触できない場合はどうすれば良いでしょうか。
この場合であってもその者を抜きにした遺産分割協議書を作ることはできません。
それでは事態が進まないので、特別な手続きをして事を進める必要があります。
連絡が取れない者に代わって一時的に相続財産を管理する「不在者財産管理人」の選任手続きを家庭裁判所で行います。
不在者財産管理人とは何らかの財産の所有者が行方不明などで居所に戻ってくることが期待できない場合などに、その財産を管理するために設けられる管理人のことです。
相続事案以外でも債権回収などの事案で財産の所有者と連絡が取れない場合に利用されることがある法的な制度になります。
不在者財産管理人は自分で誰かにお願いするのではなく、必ず家庭裁判所で選任手続きを経ることが必要です。
相続事案の場合はさらにこの管理者に遺産分割協議に参加してもらわなければ話が進みませんが、権限の関係で管理者を立てただけでは分割協議には参加できません。
そのため家庭裁判所での管理人の選任手続きの際に「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申立てを行っておきます。
こうすることで管理人は不在者に代わって遺産分割協議に参加することができます。
不在者に代わって参加することになるので、その者の利益を害さないように話し合いを行うことになります。
■失踪宣告を利用する方法
上記は相続する権利を持つ者が生きている仮定の話ですが、住民票など書類上は生存をうかがわせるものの、連絡しても音沙汰なし、実際に訪問したり捜索しても所在を突き止められず音信不通が何年も続いている場合にはすでに死亡していることも考えられます。
そのような場合には失踪宣告という制度を利用することもできます。
失踪宣告とは戦争や船舶の沈没、震災などが原因で生命の危機に会いその生死が1年間明らかでない時や、そのような特別な事態でなくとも7年間行方不明が続き生死が明らかでない時などに、法律上その者を死亡したとみなす制度です。
人を勝手に死亡したことにしてしまうということで重大な権利侵害につながる危険もあるため、こちらもやはり家庭裁判所での手続きが必要になります。
戦争などでない生死不明の場合には、最後の生存確認から起算して7年間を経た時点で死亡したという扱いになります。
死亡扱いになるため、その者に子がいる場合は代襲相続が発生することになるのでケースによってはなお波乱含みになる可能性を残します。
またもし後になって生存が発覚した場合は色々面倒なことになります。
実は失踪者が生きていて、後から「自分はまだ生きている」と失踪宣告を取り消す手続きをしてこれが認められた場合、すでに作成した遺産分割協議書は無効とはなりませんが、もし残っている遺産があった場合は原則としてこれを返還しなくてはならなくなります。
このようなこともあり失踪宣告は気軽に利用できるものではありませんが、場合によっては検討することもあります。
■専門家を利用するのが無難
色々見てきましたが、連絡を取ったことがない相続人がいる場合、第三者の専門家を利用するのが安心安全です。
連絡先が分かっているケースでも、それまで接触したことがない相手方にコンタクト取るのは緊張や拒否感を生んでしまうことが多く、話がこじれてしまう要因になります。
ここに例えば第三者の弁護士や顧問税理士などから第一報の連絡をしてもらうことで、間に人が入る分心理的な摩擦を抑えてスムーズに接触することが期待できます。
手間がかかる相続人調査(戸籍調査)では専門家を利用することも多いので、その場合は相手方への連絡第一報を代わってしてもらうようにお願いしてみましょう。
裁判所での手続きが必要になる不在者財産管理人の申立てや失踪宣告などは弁護士や司法書士が担当しますが、個別に依頼するよりも普段から顧問をお願いしている専門家を窓口にすれば連携している専門家が動いてくれるので、ワンストップで手間がかかりません。
手続き面だけでなく、遺産分配は利害が絡むので自分たちだけで処理してしまうと後から問題が持ち上がることも考えられます。
専門家をうまく活用して間違いの無い相続処理を目指したいものです。
相続税の申告と納付について
相続税という税目が疎まれやすいのは税金を取られるという単純な理由もありますが、制度や仕組みが分かりにくいというのが大きな理由です。
相続税は「申告」と「納付」という二つの作業に分かれますが、その両方必要な人と申告のみが必要な人、両方不要な人に分かれます。
所得税と同じように自己申告制を取る相続税は、申告と納付の必要性も自分で調べて判断するしかありません。
法律上必要な申告や納付を怠れば相続税法違反となり金銭的なペナルティを課せられることもありますし、場合によっては懲役刑に処せられることもあります。
意図した脱税ではなくとも税務署にとっては追加徴税などで多く徴税できるチャンスですから容赦してくれません。
そこで今回は相続税の申告と納付について詳しく見ていくことにしましょう。
■相続税の申告と納付が不要な人とは
まずは申告と納付が「絶対的に必要のない人」を確認してみましょう。
これに該当すればあなたは相続税の申告も納税も不要です。
相続税には基礎控除という枠があり、相続財産がこの額以内であれば課税額は0になるので納税が不要なのはもちろん、申告自体も不要になります。
近年この基礎控除枠が縮小され、税負担が発生する人が増えるとされています。
現在の枠は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。
例えば法定相続人が三人であれば4800万円までの相続財産であれば相続税の申告も納付も不要です。
相続税の難しいところは遺産をそのままの額で評価できないという所にもあります。
自分で正味の遺産以外の色々な数字を足したり引いたりする計算を強いられます。
相続財産の数値化や債務控除など足し引きの計算方法については別の章を参照してくださいね。
■相続税の納税が不要でも申告の義務がある人とは
では次に、相続税の納税は必要ないけれど申告自体は必要な人とはどういう人か見ていきます。
相続税の処理ではまず相続財産を全て数字に直すことから始まります。
財産を数値化して課税標準を定めないと税率をかけて税額を算出できないからです。
そして計算上、厳密には遺産でないものも色々と相続財産に加えたり、逆に控除したりする作業が入ります。
そこから上記の基礎控除額をさらに控除し、残った額に一定の税率をかけて税額を算出します。
さらにここから税額控除といって一定の額を算出された税額から引くことができる場合もありますが、税額控除を適用した結果税金額が0以下になった場合でも申告だけは必要なこともあるので注意が必要です。
またそれ以外にも税負担を軽減する特例を使って税額を0以下にした場合は例え納める税金の額が0でも申告だけは必要になります。
申告を怠るとただの申告漏れ扱いとなってしまうので要注意です。
例えば多くの人が使える大きな減税措置である「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」などを利用した場合は例え税額が0になったとしても申告書の提出だけは必要になります。
■相続税の申告書の提出先は
相続税の申告先は原則として被相続人の生前の住所を管轄する税務署になります。
相続税は被相続人ではなく相続人に対してかけられるため、自分の住所に最寄りの税務署と勘違いする人が多いです。
遠方の実家で相続が発生した時にはその地元の税務署に対して申告しなければなりません。
例外として、被相続人が外国で死亡した場合の取扱いがあります。
アジア圏など生活費が安い海外で老後を過ごす方も増えていますから、この場合は取扱いが異なります。
まず、被相続人が海外で亡くなっても、その相続人が日本国内に居住していれば「居住無制限納税義務者」という扱いになります。
この場合は当該者の住所地の管轄税務署が申告先となります。
また、「非居住無制限納税義務者」という扱いもあり、相続発生時に日本国籍を有しておりながら日本国内には住所を有していない者などは住所地管轄がないので、改めて納税地を定めて申告しなければならないことになっています。
詳しくはこちらで確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138_qa.htm
■相続税の納税が必要な人とは
相続税には様々な控除措置や特例が用意されていて、これらを利用することで計算上の税負担が0になる場合があります。
基本的な債務控除や基礎控除は誰でも使えますが、特例などは個々人によって使える人とそうでない人がいます。
こうした控除や特例を使って計算をしてもなお税負担が生じた場合には申告だけでなく納税も必要になります。
申告と納税の期限は同一で、相続発生の翌日から10か月以内となっています。
税の納付は税務署でも行えますが金融機関などでも可能です。
この期限を逸すると延滞税などペナルティが発生しますので注意してください。
納税は金銭で一括納付が必要ですが、遺産のほとんどが不動産などの場合は納税資金を用意することが難しいこともよくあります。
どうしても期限までに納付が難しい場合は延納や物納が認められることもあります。
■延納と物納の制度
延納とは分割払いの方法を用いて納税期限を伸長しながら少しずつ納める方法です。
物納は文字通り金銭以外の一定の財産でもって納税する方法をいいます。
どちらも必ず認められるというわけではなく、事情を説明してどうしても納税が難しいと税務署が判断した場合に限り認められるものです。
延納が認められるには納付額が10万円を超えること、一定の担保を提供することなど一定の条件を満たさなければなりません。
担保に供することが認められるのは国債や地方債、社債、土地や建物などに限られます。
延納制度を使うには利子税を納めることも要求されます。
相続財産に占める不動産の割合が大きいほど、納税資金を用意することが難しいと判断されて利子率や最長延納年数などの面で有利になる仕組みです。
ちなみに利子税は年一回の元金均等払によって納めます。
延納と物納には優先順位があり、最初から物納を検討することはできません。
まずは延納を検討し、それもダメな場合にのみ物納が検討されます。
物納できるのは被相続人が残した相続財産に限られ、相続人固有の財産は利用できません。
また国による利用を考えて、国内に存する財産しか利用できません。
物納に利用できるものは限られ、それらにも優先順位が設定されています。
まずは国債や地方債があれば最優先で利用されます。
それがなければ次は不動産や船舶、それもなければ社債や株式など、されにそれもない場合には動産も利用可能です。
ただし質権や抵当権の目的となっているものは利用できません。
物納では利用されるその物品をどうやって評価するかが問題となります。
金銭価値を判断しないと納税にならないからです。
これを「収納価額」といいますが、収納価額は相続が発生した際の相続税評価額となります。
相続税評価額というのは金銭以外のものについて、相続税の税額計算の為にその価値について判定したものです。
例えば不動産であれば、単に不動産屋の査定額が相続税評価額となるわけではありません。
国が定めた一定の評価法に従って算出されるもので、全国どこでも同じ基準で判断ができるように国がその評価法を定めています。
「財産評価基本通達」といって、相続税の計算の為に遺産を数値化するためのルールとして決められています。
これによって地域によって財産の評価にズレが生じて不公平感がでることなどを防ぐことができます。
相続人と相続分の関係
最近は人間関係が希薄になってきたため、親戚付き合いをあまりしないという方が増えているようです。
普段は余計な付き合いをしないことで余計なトラブルもまた避けることができるということもあるのかもしれませんね。
ただ人が一人死ぬということは、その方と関係する一定の血縁者は否応なく相続事件に巻き込まれるということになり、ここで近親者や普段付き合いの無い親せきとの揉め事に発展することもあります。
相続事件では関係する者同士は利害関係者となるので、余計な入れ知恵や虚偽のアドバイスなどが横行する可能性もあります。
自分の、あるいは自分の配偶者や味方の利益を増やそうと他者を陥れるような行為も起き得るのです。
ですから相続に関して正しい知識を持つことは自衛の面でとても大切です。
今回は相続が発生した際の相続人の種類や取り分について見ていきましょう。
■誰が相続人になる?相続人と法定相続人
たまに聞かれる質問として相続人と法定相続人は違うの?という疑問があります。
法定相続人というのは法律があらかじめ想定している相続人のことで、日本では民法という法律がこれについて規定しています。
法定相続人は複数想定されていますが、これらの者が全員必ず相続人となるわけではありません。
相続人となる権利はあるものの、具体的なケースに当てはめるとその権利を行使できる者は一部に限られてくるのです。
法が想定している相続人は以下の者です。
「配偶者」
被相続人と法律上の婚姻をした者です。内縁の妻など事実婚の相手方は対象外となります。
「子」
被相続人の血を継いだ子です。
「直系尊属」
被相続人の上の世代の親や祖父母などのことです。
「兄弟姉妹」
被相続人の兄弟姉妹を指します。
上記が基本的な法定相続人です。
このうち配偶者は生きてさえいれば必ず相続人となることができるのですが、それ以外の者等はそうではなく、優先順位があるのです。
基本的には上から順に「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順に優先され、例えば子がいる場合は直系尊属と兄弟姉妹は相続権を持ちません。
被相続人に子がおらず、親も死亡している場合はすぐに兄弟姉妹にはいかず、その前に親の親、つまり祖父母がいればこの者が相続人となります。
年齢的には難しいかもしれませんが、直系尊属は生きていさえすればどんどん上の世代にさかのぼって相続人となります。
子も直系尊属もどちらもいないというときにようやく兄弟姉妹に順位が下りてくるという具合です。
優先順位があるこれらの者は配偶者も生きていれば両者が相続人となります。
ただし、この順位で注意しなければならないのが「代襲相続」という決まりです。
代襲とは本来の相続人が被相続人の死亡時にすでに死亡していた場合など、すぐに次の順位者に権利が移らず、その被代襲者の子が代わりに相続権を持てるというものです。
代襲が認められるのは子と兄弟姉妹のみです。
しかしこの両者には扱い上違いがあります。
子の方はもし死亡していてもその下の世代が生きていればどんどん代襲が続き(再代襲、再々代襲として)子の子、さらにその子と続いていきます。
しかし兄弟姉妹の方はその子までの一世代限りの代襲で終わりです。
それ以下になると血のつながりが薄くなるので法律は優遇しないのです。
さて、このようにして相続人が決まっていくのですが、ここで冒頭の疑問が解決します。
相続人とは、これら法定された相続人のうち実際に相続権を得た者のことです。
例えば配偶者と子、配偶者と直系尊属、あるいは兄弟姉妹だけということもあるでしょう。
ただし、上記は被相続人の遺志である遺言がなかった場合に備えて法律が用意した決まりであり、遺言がある場合は原則として遺言の内容が優先になります。
例えば配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹全員に何らかの財産を承継させたい場合はそれぞれに対象財産を相続させる旨の記載がされます。
この場合は故人の遺志により原則として上記の者が全員相続人となります。
遺言で相続人となることができても、自身の判断で相続放棄をすれば相続人とならないこともできます。
ということで遺言書がある場合でもない場合でも、相続人とは「結果として」相続権を行使できる人と言うことができますね。
■相続分の取り分はどれくらい?
上記の各相続人はどれくらいの取り分となるのでしょうか。
この点は遺言書がある場合と無い場合で扱いが変わります。
遺言書がある場合は故人の遺志が優先されるので、原則として遺言書の内容通りの取り分となります。
ただし、相続人は全員の合意の元で独自に取り分を変えることもできます。
あまりにも不合理な遺言が残された場合を想定して法律が認めているものですが、遺産について分割協議を行って合理的な分割内容を実現することができるのです。
協議がまとまったらその合意内容は書面の形にして残しますが、これを遺産分割協議書といいます。
当事者同士で協議がまとまっても、第三者はそれを目で見て確認することができません。
不動産の登記の際などに担当官に正式な権利者としての証明をしなければならず、そのような場面で遺産分割協議書は活躍してくれます。
ただし複数相続人のうち誰か一人でも反対すれば協議はできず、やはり遺言書の内容が優先されます。
では遺言書がない場合はどうなるでしょう。
この場合も法律は想定していて、各相続人の取り分(法定相続分)を決めています。
必ずしも法定分通りの分割にしなくとも、これを指標にして調整をした分割内容にしても構いません。
民法で法定された取り分は以下のようになっています。
・相続人が配偶者のみの場合・・配偶者が全額
・相続人が配偶者と子の場合・・配偶者が二分の一、子が二分の一
・相続人が配偶者と直系尊属の場合・・配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一
このように、法定相続人は相続分についても優先度があり、配偶者と子が一番優遇されるような仕組みになっています。
ちなみに、子が複数いる場合、親などが両親とも生存している場合、兄弟姉妹が複数いる場合などはそれぞれは均等の取り分となります。
例えば被相続人の配偶者と子が二人相続人となる場合は配偶者が二分の一、二人の子はそれぞれ四分の一ずつの取り分となります。
■遺留分について
遺言がある場合は原則として遺言が優先されるとお話しましたが、中には全遺産を愛人に譲るなどの遺言が書かれることもあります。
こうした場合遺族があまりにもかわいそうですね。
そこで法は「遺留分」というものを用意していて、一定の法定相続人には最低限の取り分を確保することができるようにしています。
遺留分の権利があるのは配偶者と子、それに直系尊属のみです。つまり兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の取り分としては直系尊属のみが相続人となる場合は法定相続分の三分の一、それ以外の場合は法定相続分の二分の一となります。
ただし遺留分を確保できるのはあくまで当人がその遺留分の主張をした場合だけです。
この主張をしなければ遺留分があったとしても手元には入ってきません。
遺留分の主張は他の相続人等財産の承継を受けた者に対してしなければなりません。
主張の方法は口頭でも不可能ではありませんが、主張の証拠を残さなければ実質上の救済を受けられなくなる恐れがあるので内容証明郵便などを用いて「遺留分減殺請求」として行うのが普通です。
子なし家庭が注意すべき相続の注意点6点
近年、若い世代でもじわじわと子供がいない世帯が増えていますね。
自身の相続を考える世代の方々の中にも様々な理由で子供のいないご家庭もあります。
遺言講座や高齢者向けのファイナンシャルプランニングサービスでは夫婦二人と子どもが1人~2人程度のケースを想定して解説されることがほとんどですが、相続というものに視点を絞った場合、子どもがいる場合といない場合とでは対策の立て方が異なります。
今回は一つの悲しい実例を挙げながら、これを軸に子供のいないご家庭で相続対策を考える際の注意点を見ていきましょう。
■配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースは警戒度MAX!
我が国の法制度は相続に関しては民法上で基本的な決め事が設定されています。
どんなケースで誰にどれだけの財産が相続として承継されるのかといった基本事項が決められているわけです。
夫婦に子供がいない場合誰が相続人になるのかもこの中で決められていて、場合によっては何も対策をしないと長年連れ添った配偶者が住居を追われる可能性も出てきます。
ここで実際に起きた最悪の事例を一つご紹介しましょう。
旦那さんは奥さんと一緒に暮しておりましたが子どもがいませんでした。
彼も75歳と高齢で、親はすでに亡くなっています。
旦那さんは自分には子どもがいないので自分の死後は当然に奥さんが全て相続するものだと思い、特に対策などは行っていませんでした。
そして旦那さんの死後にはわずかな現預金と住居の一軒家だけが残されました。
奥さんはその家で慎ましく暮らしていくつもりだったのですが、ここに旦那さんのお姉さん(Aさんとします)が登場します。
奥さんとAさんは普段は付き合いはありません。
一般的に自分の配偶者とは当然仲が良くても、その兄弟姉妹と仲良くするというケースは稀と言って良いでしょうね。
奥さんもそうだったわけですが、ここでAさんが自分の遺産の取り分を主張してきました。
奥さんはビックリしましたが、喧嘩もしたくないので弁護士に相談して相応の取り分を分けて上げようと思いました。
しかし現預金がわずかなため家を売るしかありません。
家も古いため高額では売れず投げ売りになりました。
奥さんは次の住居を探しましたが高齢者には孤独死や自殺、未納のリスクがつきまとうためなかなか貸し手が見つかりません。
理由がどうであれ、人が死亡するとそのアパートなりマンションなりの価値が激減してしまうからです。
奥さんは何とか行政の助力も得てアパートを見つけることが出来ましたがほとほと疲れ果ててしまい、心労で体を壊してしまったそうです。
相続事案を扱う弁護士や税理士の間ではあたりまえのこととして語られる逸話です。
ですから配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になることが想定される場合、必ず早めに遺言書の準備をしておくようにアドバイスします。
この事例では内容は至極シンプル、「全ての財産を妻の〇〇に相続させる」という趣旨の内容にすれば何も問題は起こらなかったのです。
なぜこのようなことが起こるのか、次の項で見ていきます。
■遺言書の内容は原則として民法の定めよりも優先する!
先ほどの事例は故人(被相続人)の兄弟姉妹も法律上の相続人として相続分の主張ができることを知らず、対策を怠っていたためです。
民法が定める相続人は次の通りです。
配偶者:生存していれば必ず相続人となる
第一順位:子
第二順位:被相続人の直系尊属(親や祖父母など)
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
まず配偶者は生きていれば必ず相続人となります。
ですから上の実例でも奥さんは相続人になることができました。
しかし配偶者以外にも、優先優位が高い順に生存していれば相続人になれるのです。
実例では第一順位の子と第二順位の親もいません。
この場合親のさらに上の世代、祖父母が生きていれば相続人となりますが、高齢ですでに死去されていました。
残ったのが第三順位の兄弟姉妹、実例では姉のAさんです。
つまりこのケースでは奥さんと兄弟姉妹のAさんが相続人として正当な権利者となり、相続分を主張できるということになります。
この例では奥さんは全遺産の4分の3、Aさんは4分の1を主張できます。
現預金が多ければ現金で支払うこともできるでしょうが、日本の相続では不動産が多くを占めるのが普通で資金を準備できないことも多いのです。
そのため不動産の現金化が必要になるのですが、往々にして満足のいく売却額とはなりません。
もしこの時、旦那さんが「全ての財産を奥さんに相続させる」旨の遺言書を作っていたらどうでしょう。
実はこの場合、原則として民法の定めよりも遺言書の方が優先されるので、Aさんは取り分の主張をすることができず、奥さんは全ての財産を貰い受けることができます。
ですから住み慣れた自宅を追われることはなかったのです。
これは完全に旦那さんの理解不足、対策不足でした。
ちなみに、遺言書が無い場合の法定の取り分(法定相続分)はケースごとに以下のようになります。
もし自分が遺言書を準備しないで死亡したら、誰にどれだけの遺産が渡ることになるのか想像してみましょう。
・配偶者と子が相続人となるケース
配偶者と子が2分の1ずつ。子が複数の場合は均等に分ける
・配偶者と直系尊属が相続人となるケース
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
・配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケース
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
これを見ると、法律は血縁関係よりも実生活で伴侶となった配偶者を優遇し、次いで血縁が濃く精神的な繋がりが強い順に優先されているのが分かりますね。
ただしこの規定は遺言書が無い場合を想定して法が準備しているものですから、先ほどお話したように遺言書がある場合は原則として遺言の内容が優先になります。
従って例えば配偶者には何も残さず、姉のAさんに全ての財産を相続させる旨の記載があればそれが優先されることになります。
この遺言の内容を覆したい時は、相続人などの権利者が全員合意の元で話し合って自由な取り分を決めることができます。
冒頭の実例では、奥さんと姉のAさんが双方の合意の元で「奥さんだけが相続する」旨の取決めをすれば奥さんは救われていましたが、情や繋がりが薄い相手にそこまで譲歩することは期待できません。
従ってやはり遺言書の準備は非常に重要ということになるのです。
■遺留分にも注意!
上の項で、例えば姉のAさんに全財産を相続させる遺言にすることも可能とお話しました。
確かにそれは可能です。
しかし法律は遺言書でも覆すことができない、ある規定を設けています。
それは「遺留分」という権利です。
遺留分は一定の相続人に最低限の取り分の主張を認めたものです。
ですから例え遺言書で遺留分を無視した分配(『遺留分を侵害する』といいます)内容にしたとしても、遺留分を持つ権利者が主張すれば、最低限の遺留分の取り分を主張できることになります。
この点、遺留分はあくまで「権利」であって当事者が主張しなければ遺留分の権利は行使できません。
ですから遺言で誰かの遺留分が侵害されていても、その人が納得している場合や、何らかの見返りを受けることで遺留分を主張しなければ遺言書の内容が実現できます。
もしこの権利を主張する場合は「遺留分減殺請求」という形で主張することになります。
遺留分の権利者は配偶者と子及び直系尊属だけです。
そしてその遺留分は次の通りです。
・直系尊属だけが相続人となるケース
法定相続分の3分の1
・上記以外のケース
法定相続分の2分の1
上記の通り、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
ですから奥さんが住居から追い出された冒頭の実例で、旦那さんが「妻に全財産を承継させる」旨の遺言書を作っていたら、姉のAさんは遺留分の権利主張もできないので、奥さんは遺言書によって完全に守られることになります。
逆にもし、「姉のAに全財産を相続させる」旨の遺言内容だった場合には、奥さんは法定相続分の2分の1の遺留分の権利を主張して、姉のAさんに対して遺留分減殺請求をかけることによって遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求は、その請求の証拠が残るように内容証明郵便などで行うようにします。
なお、この「遺留分」の規定ができた背景には、親族や情が通った配偶者などが相続の場面で理不尽な扱いを受けないようにという配慮があります。
例えば、家族を顧みず遊びにほうけて外で作った愛人などに全財産を譲るなどという事例も無いわけではありません。
実際似たような事例は今でも見聞きしますよね。
これでは家族が余りにもかわいそうだということで、法律によって一定の者に遺留分の権利を保証したのです。
■代襲相続にも気を配ること!
冒頭の実例で、もし姉のAさんも亡くなっていて、他に兄弟姉妹もいなければどうだったでしょうか。
第三順位の兄弟姉妹までいないことになるので、残った奥さんだけが相続人となって安泰でしょうか。
実はまだ安心できません。
民法には「代襲相続」という規定があり、一定の相続権利者が被相続人の死亡前にすでに死亡していた場合、その下の世代が上の世代の相続権を受け継ぐことができることになっています。
冒頭の実例では、姉のAさんが亡くなっていたとしても、Aさんに子があれば(仮にBとします)、BがAさんに代わって相続人(代襲相続人)となります。
ですから遺言書がなければやはり奥さんはBさんに法定相続分の取り分を持っていかれることになります(Bさんが任意で遺産を受け取らないことはできます)
また代襲相続人は被代襲者(死亡していなければ相続人となっていた者)の権利をそのまま引き継ぎます。
そのため遺留分の権利がある者を代襲した場合は代襲者も遺留分の権利を行使できますが、元々遺留分の無い被相続人の兄弟姉妹の代襲者は遺留分の権利はありません。
今回の事例では姉のAさんが亡くなっていてその子Bが代襲したとしても、「全財産を妻に相続させる」旨の遺言があれば遺留分の権利も行使できませんから奥さんは完全に守られ、安住の住処で暮らすことができます。
ちなみに、代襲相続が認められるのは子と兄弟姉妹のみで、直系尊属には認められません。
また子の代襲は下の世代が生きていれば永久に認められますが、兄弟姉妹の代襲は1世代のみ、つまり当該兄弟姉妹の子までしか認められません。
■妻以外の女性の子も相続人になる!
もう一つ盲点になることをお話します。
前述した通り、相続人になり得るのは配偶者の他に子、直系尊属、兄弟姉妹がいます。
そして子と兄弟姉妹には一定の代襲相続が認められることもお話しました。
このなかで「子」とは、何も直前まで婚姻関係にあった配偶者との子に限られません。
つまり前妻の子も第一順位の相続人と成り得るのです。
実際の事案で隠し子が発覚して大問題になるのはこのためです。
結婚を何度か繰り返している方が亡くなった場合、以前の配偶者との間に設けた子は立派な相続人です。
今回の事例では前妻は出てきませんでしたが、もし旦那さんに前妻がいて子(仮にCとします)がいる場合は姉のAさんではなく、優先順位の高い子であるCが奥さんと共に相続人となります。
この場合旦那さんの姉Aさんよりもさらに情関係がないCは容赦なく奥さんに自分の取り分を請求してくることでしょう。
ただしこの場合もやはり遺言書の準備があれば奥さんを守ることができるのは変わりありません。
とにもかくにも、遺言の準備が大切なことがお分かりいただけたでしょうか?
遺言はどんな場合でも準備するに越したことはありませんが、子どもがいないケースでは特にその重要性が増すのです。
■専門家に相談する場合の注意点
登場人物が増えるほどに関係は複雑になり、誰がどんな権利を持つことになるのか分かりにくくなります。
これから自分の人生の終わりの準備をしようと思っている方はぜひ万全の準備と対策を心がけたいものです。
自分だけで処理しようとすると、知識不足や情報不足から思わぬ落とし穴にはまってしまう危険があるので、専門家へ相談することも有効です。
その時には権利関係を一つ一つ丁寧に説明する必要があり、隠し子などがいる場合でも正確に伝えなければ正しいアドバイスを受けることができず、かえってマズイことになってしまう公算が大ですから正直に話すようにしましょう。
親族関係図などを作っていくと呑み込みが早くなるので相談を受ける側としてはかなり助かります。
肝心の専門家選びとしては弁護士、、税理士、司法書士、などが適応になりますが、いずれも相続問題に明るい人材を選ぶようにしましょう。
各専門家とも実際は取扱分野が広く、相続関係には明るくなかったりします。
不動産を相続した時にするべき4つの手続き
相続が発生すると、故人が生前に所有していた財産が相続財産として相続人等の権利者に承継されることになります。
我が国の相続事情は相続財産に占める不動産の割合が高いという特徴があります。
特に地方では持ち家率も高く、老齢の親が亡くなった場合にその住処が相続承継の対象になります。
また不動産は相続税の対策としても有効で、現預金よりも相続税評価額が低くなるため、税負担を減らすために現預金を積極的に不動産に変える(購入する)ことが多いことも理由の一つです。
そのため日本国内の相続事案ではほとんどの場合不動産の承継が行われることになります。
今回は不動産を相続した場合の手続きや注意事項について解説していきます。
■手続き1:遺言書の検認手続きまたは検索・照会請求
近年、「終活」や「墓じまい」などがブームになっていますが、高齢化が進む現代では自身の命の終焉に向けて必要な準備をするという意識が高まっているのが分かりますね。
元々このようなブームに関わらず、わが国には「遺言」という法的なルールがあり、自分の生前の財産の分配などについて後の世代に引き継ぐ手段として活用されてきました。
遺言の内容を書面に記したものが「遺言書」となるわけですが、相続争いを防ぐためにも有効であることが広く浸透していますので多くの事例で遺言書が作成されます。
この遺言書は扱いに注意しなければならないことをご存知でしょうか?
あなたが故人の家族で相続人となる場合、タンスの引き出しから遺言書が出てくるかもしれませんね。
よくテレビドラマなどでは親族が一堂に会して故人の遺言書を開封する場面がありますが、これをしてしまうと法律違反になってしまいます。
「過料」といって一種の罰金を取られてしまうこともあるので注意が必要です。
タンスなどにしまわれた遺言書は「自筆証書遺言」といって、故人が自筆で作成して保管していたものです。
自筆証書遺言は偽造や変造の可能性があるため、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
検認は裁判所が関与することで全ての相続権利者に対してその通知を行い、相続が起きたことを知らせる意味もあります。
そのため相続人を確定させなければならないので、故人(被相続人)の方の出生時から死亡時までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
詳しくはこちらで確認できます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/
ただし遺言書は公証人が関与して作成される「公正証書遺言」で作られることもあります。
この場合は検認作業は必要ありません。
公証人とは裁判官や検察官、弁護士など法律に関わる仕事を長年してきた一定の者が法務大臣によって任命される公務員です。
法律の専門家が関与して作成され、公証役場に原本が保管されているので偽造や変造の心配がないので検認をしなくてもよいことになっています。
故人が生前に公正証書遺言を作成したことを話している場合は最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。(遺言書の検索・照会請求といいます)
また正本(写しのようなもの)の交付がされているはずですから、これを発見した場合も当該公証役場に問い合わせが必要です。
■手続き2:相続を原因とする所有権移転登記
我が国では不動産の権利について明確にするために「登記」というシステムが取られています。
土地や家屋などの不動産に所有権や抵当権などの権利がある者は、これを登記システムに反映させることでその権利を明確にし、他者による権利侵害を防ぐことができます。
登記システムは法務局が管理しており、登記手続きも法務局で行います。
相続によって不動産を取得した場合は相続を原因とする所有権移転登記を行うことによって自分の権利を第三者に有効に主張することができるようになります。
この登記は法律上は必ずしなければならないものではなく、その期限も特に定められていないため先延ばしにしたり失念するケースも散見されますが、他者による権利侵害やいざその不動産を売却しようとするときに上手くいかなくなったりと、色々と不具合が出る危険性が非常に高いので登記手続きは必ず行うようにしてください。
所有権移転登記はよく「名義変更手続き」などとして紹介されることがありますがこれは正確ではありません。
名義変更というのは実際は本来の所有者の住所の変更登記のことなので別の手続きになるのですが、イメージ先行で所有権移転登記のこととして呼称されることもあります。
また所有権移転登記には売買を原因としたものと相続を原因としたものがあり、それぞれ手数料の税率が異なります。
相続を原因とするものはその不動産の固定資産税評価額の0.4%の税率がかかり、手数料として登録免許税という税金の形で納付することになります。
登記作業に必要になる書類等はケースによって異なります。
有効な遺言書がありそれに従って不動産の権利を承継する場合は比較的手間がかかりませんが、そうでない場合には法務局にその不動産の権利を誰が正当に取得したのかを説明、証明するために色々な資料が必要になることがあります。
まず複数相続人同士で自由に不動産の権利を定めた場合は、その約束事を確認できる遺産分割協議書が必要です。
またその協議に参加した者が正当な権利を有する者であることを証明するために、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になります。
他に必要な物としては被相続人の戸籍謄本や登録免許税の額を算出する指標とするためにその不動産の固定資産税評価証明書も必要になります。
素人ではなかなか手間がかかり面倒なので司法書士などに依頼するケースも多く、その場合は数万円程度の報酬が必要になるでしょう。
■手続き3:相続税の申告と納税
相続財産に不動産を含むか含まないかに関わらず、我が国の税制では相続財産は課税の対象になります。
日本の税金はお金や財産価値のあるものが人や法人の間で移動した時に課税するのが基本ですが、相続では故人から相続人などに財産が移転するので、ここに目を付けられた形です。
相続財産に対してかけられる税目を相続税といい、この手続きのことを考えなければなりません。
相続人など遺産を貰う立場の方が覚えておかなければならないのは、例えば5000万円の不動産を相続で承継したからと言って、単純にこれに相当する相続税を納めるわけではないということです。
相続税は不動産以外の現預金や有価証券など全ての財産を合算して考えなければならないのです。
そしてもう一つ大事な「基礎控除」の存在は絶対に知っておきましょう。
これは相続という人の死に対してかけられる税金に対する国民感情への配慮のため、一定の額の遺産までは相続税の課税を免除するために作られたものです。
近年この基礎控除の枠が減ってしまい、税負担が増える方が増加してしまいましたが、それでもかなり大きな控除枠の為多くの事例で相続税の負担を無くしたり、税金額を減らしたりする効果があります。
計算式としては、「基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
この額の遺産までであれば相続税がかからないので納税だけでなく申告も不要になります。
基礎控除は非常に有効で大切なので掘り下げて解説します。
遺産の価値は誰が判定するのかというと、基本的には税務署ではなく相続人等の権利者が自分で考えます。
問題になるのは素人が相続財産の評価をしなければならないということです。
相続税の額を算出するための「相続税評価額」というものを算定しなければならないのです。
現預金はそのままの価値ですが、不動産の価値はどのようにして判定するのでしょうか。
実はこれが素人には非常に厄介で、その不動産が土地か建物かによっても評価方法がわかれます。
土地の場合は市街地等にある物件の場合基本的には「路線価」という指標を用います。
土地は国によって一定の基礎評価を受けており、これを路線価という形で公表しています。
しかしこれは国が定める基本の指標であり、実際にはそこに様々な補正を加えて実際の不動産の価値を判定しなければなりません。
例えば当該物件が自宅の土地など自分で使用する自用地なのか、アパートなど他人に貸すための土地なのかによる利用形態による補正、その土地が所在するエリアが住宅地区なのか、商業地区や工場地区なのかなど区分による補正、道路に面するところからどのくらいの奥行きがあるのかによる奥行補正、角地や準角地などによる影響補正など様々な補正を施さなければならず、正直なところ素人ではかなり難しい作業になります。
路線価が無い郊外などの土地は「倍率方式」、宅地以外は宅地比準方式が適用になったりと複雑です。
家屋の評価は土地よりは複雑ではないものの、貸家などの場合は借家権割合の調整などが必要になります。
また政府が用意した特例や特別控除など、不動産の価値を計算上下げて、もって相続財産の額を減らし、相続税の負担を減らす措置が用意されています。
これは知っていなければ利用できませんが、上述したように非常に手間がかかるうえに複雑なため、相続税の申告や納税は税理士などの専門家に依頼すると安心で安全です。
税理士はその筋の専門家ですから、特例なども上手く活用して税負担を極力減らすようにしてくれるでしょう。
自分で行う場合はさらに基礎控除の枠に収まるように、非課税財産や債務控除などの概念をフルに活用して相続財産額を計算上減らす工夫が必要です。
非課税財産とは厳密に言えば故人の財産と言えるものでも、国民感情への配慮や政策上の取決めによって遺産の総額に算入しなくても良いものをいいます。
例えば墓地や仏具、あるいは香典など一定の葬儀関係の財産や、生命保険金の一部、退職手当金の一部、一定の寄付や公益事業用財産などがあります。
生命保険金と退職手当金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税財産とすることができます。
債務控除とは故人が持っていた一定の債務を相続財産から控除し、遺産額を減らすことができるものです。
例えば借入金や未払いの医療費、未払いの住民税や固定資産税など一定の税金、通夜の費用や葬儀費用、葬儀前後で通常必要とされる出費などです。
控除できないものもあり、墓地購入にかかる未払い金、弁護士費用や税理士費用、土地の測量費用や登記費用、香典の返戻費用、故人の死後の墓地購入費用などは控除できません。
さらに、逆に相続財産に算入しなければならない「みなし相続財産」というものもあります。
本来は故人の財産とは言えないものでも、実質的に故人の権利に帰属するとみなされるものです。
一定の生命保険金や生命保険契約に関する権利などがあります。
注意が必要なのが相続開始前3年間になされた相続人への財産の贈与を相続財産に組み戻す「3年以内の贈与財産の加算」です。相続税逃れのために生前に財産移転する行為に対する牽制の効果があるものです。
同加算とみなし相続財産は遺産の総額を増やす方向に働くものですが、税理士などの専門家を利用しない場合はこれらも相続人が自己の責任で計算しなければなりません。
こうした計算の結果、基礎控除内に収まれば相続税の申告納税は不要になります。
基礎控除を超えた場合はさらに相続人個人個人の事情を反映した複雑な計算をして最終的な相続税額を算出し、税務署に対して申告、納税を行います。
■手続き4:固定資産税の納付
不動産は実は所有しているだけで税金がかかるという厄介な側面も持っています。
今まで不動産を所有したことがないという方でも「固定資産税」という名前は聞いたことがある人が多いと思います。
固定資産とはつまり不動産のことを指しており、これが所有しているだけで課税される税目になります。
固定資産税は国税である相続税と違って市町村税となり、管轄もその不動産の所在を管轄する地元の市区町村です。
相続税と違って固定資産税は地元の役所が勝手に不動産の財産評価をし、必要税額を算出して納付書を送ってきますので、これに従って納付することになります。
固定資産税の算出の為に用いる指標は相続税とは異なり、独自の指標を用いて地元の役所が「固定資産税評価額」というものが設定されます。
相続税算出の為に用いられる「相続税評価額」よりも若干低めの価値評価になるのが普通です。
納税義務者はその年の1月1日時点で所有権を有する者になるので、相続で不動産を取得した場合は翌年から納税義務者となります。
相続コンテンツ一覧
- 生命保険を使った相続税対策
- 愛人、内縁の妻に財産を相続させたい!やっぱり本妻に財産を取られる?
- 相続についてのお尋ねが届いたら
- 遺言書のトラブルについて
- 相続人が未成年の場合はどうすればいいの?
- 相続時精算課税制度のメリットデメリット
- 相続の際にも使える!不動産売却の際に使える3,000万円控除
- 知っておきたい生前贈与の種類
- 〜知って得する!相続税の仕組み〜【養子にすると節税になる?】
- 遺産分割調停の仕組みと実際について
- 受取人を変えるだけで節税に?!「相続税と生命保険の関係について」
- お墓、仏壇を購入すると節税になる?!
- 知っておきたい新制度 ”法定相続証明情報制度” とは?
- 相続財産の整理ってどうすればいいの?
- これだけは知っておきたい!!相続がおこった時のマメ知識
- 遺言書の活用~メリット・デメリット~
- 隠れたリスクがいっぱい。相続した不動産を空き家にしておく危険性
- 『気付いた時にはもう遅い?相続の準備でやっておくべき事』
- 【音信不通】連絡を取ったことがない相続人がいる場合
- 【遺産の放棄はできる?】相続放棄についてまとめました。
- 【遺産相続】相続財産評価、現預金以外の評価について
- 相続税の申告と納付について
- 相続関連手続きスケジュール
- 相続人と相続分の関係
- 今からできる相続対策!生前贈与の活用法
- 子なし家庭が注意すべき相続の注意点6点
- 子供が結婚、家の面倒見てやるか・・親から子への住宅取得等資金贈与のポイント5つ
- 不動産を相続した時にするべき4つの手続き
- お得な生前贈与をフル活用して節税する
- 相続税申告の税理士報酬はいくらくらいかかる?【相場】
提携して一緒にプロとして相続対策をしてくださる司法書士の方へ
まずはご連絡くださいませ。
その後、詳しいお打ち合わせをさせてもらえたら幸いです。
相続のプロ税理士を探されている方もご連絡ください。

【予約制】平日 11:00-18:00 / 時間外・土日対応可能